もくじ
ウザい、不快と話題の「ダークパターン」とは?
メディアなどで取り上げられる機会も増えている「ダークパターン」をご存知でしょうか?
「ダークパターン」とは、UXデザイナーのHarry Brignul(ハリー・ブリヌル)氏によって命名された用語で、スマートフォンアプリやECサイトなどのUI(ユーザーインターフェース)で、ユーザーを欺いたり、誤解させたりする目的からつくられたWebデザインを指します。
ダークパターンの問題点は、ユーザーにとって最善ではない選択をさせることにあります。実際にダークパターンによって、個人情報を悪用する不誠実な扱いや、余計な出費を強いる問題が世界規模で発生しています。
最近のケースだと、Amazonのヨーロッパ本社であるAmazon EU SARLが、悪質なダークパターンで消費者を欺いたとし、ポーランド政府から約12億円(3185万141ズウォティ)の罰金を科せられています。
Amazon(Amazon EU SARL)では以前から、消費者に十分な情報が提供を行われず、圧力をかけられているといった苦情が、ポーランドの競争・消費者保護庁(UOKiK)に相次いでいたとのことです。
ダークパターンの定義
ダークパターンの提唱者であるブリヌル氏は、ダークパターンを以下のように定義づけています。
What are deceptive patterns?
Deceptive patterns (also known as “dark patterns”) are tricks used in websites and apps that make you do things that you didn’t mean to, like buying or signing up for something. For example:
Trick wording
Sneaking
Obstruction
【引用】Deceptive Patterns
意訳すると以下のような感じ。
消費者庁サイトの説明は以下のとおり。
ダークパターンは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブデザインなどを指すとされています。
ダークパターンの行為類型は多岐にわたると考えられるところ、例えば、「残り○分」などと、あたかもその後の短期間のみに適用されるお得な取引条件であるかのように表示しているが、実際には当該期間経過後も同じ条件が適用されるもの、サブスクリプションの登録後、解約方法を一般消費者に対して不明瞭とすることで購入者の契約の解除権の行使を困難とするものなどは、ダークパターンに該当すると指摘されています。
【引用】消費者庁:ICPEN詐欺防止月間(2023年)「ダークパターンとは」
パリに本部を置く国際機関OECD(経済協力開発機構)の報告書では、以下のような実用的な定義が提案されています。
ダークパターンとは、消費者の自主性、意思決定又は選択を覆す又は損なうデジタル選択アーキテクチャの要素を、特にオンライン・ユーザー・インターフェースにおいて、利用するビジネス・プラクティスのことである。
これらは、しばしば消費者を欺き、強制し、又は操作し、様々な方法で直接的又は間接的に消費者被害を引き起こす可能性があるが、多くの場合、そうした被害を計測することは困難又は不可能であろう。
【引用】消費者庁:ICPEN詐欺防止月間(2023年)「ダークパターンとは」

ダークパターンはユーザーの心理を狡猾に利用し、だまされた側に「自分の注意不足だった」と自己責任のように感じさせる点も厄介です。
消費者庁は悪質なダークパターンの取り締まりを強化していますが、デザイン表示規制の定義にはあいまいな部分が多く、包括的なルールを設けるのが困難なのが実情です。
約3割が経験。「広告が表示され、押す気はないのに誤って押してしまった」
マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施したダークパターンに関する調査(2024年4月10日)にて、以下のような結果が得られました。
✓ アプリ・ウェブサイトの利用時に感じる不快な事象を20個呈示した中で、最も多かったのは「広告が表示され、押す気はないのに誤って押してしまった(押しそうになった)」ことで、約3割の人が経験。
✓ ダークパターンのアプリ・ウェブサイトに接触したときの気持ちは、「時間の無駄」や「腹が立つ・いらいらする」と感じる人が4割程度。約3人に1人は「もうその会社のサービスは使いたくないと思う」と回答しており、サイトを運営する企業・サービスのイメージダウンや離反も招いている様子。✓ 信頼できるアプリ・ウェブサイトとしては「企業の公式が運営しているもの」が最も高いものの、23.0%で、4割の人は「信頼できるアプリやウェブサイトはない」と回答。
✓ 「ダークパターン」という言葉の認知率は22.5%。意味まで知っている人は5.7%にとどまる。
【引用】株式会社クロス・マーケティング:-ダークパターンに関する調査(2024年)-
「ダークパターン」という言葉の認知率は22.5%で、意味まで理解できている人は全体の5.7%にとどまりますが、約3割の人が、「広告を誤って押してしまった(押しそうになった)」という経験をしています。
これは日常的にインターネットやアプリ、ECサイトを利用する人の3割もの人が、意図に反した選択や契約をさせられそうになったということです。
ダークパターン7つの分類

日本ではダークパターンを包括的に規制する法律はありませんが、ダークパターンの多くは、消費者の認知バイアス、行動バイアス、ヒューリスティックス(経験則等)を悪用することで消費者に影響を与えるものであり、OECD(経済協力開発機構)の報告書では、以下7つの手法に分類できるとされています。
①:行為の強制(例:望ましい範囲を超えた個人情報の開示を強制する。)
②:インターフェース干渉(例:事業者にとって好都合な選択肢を視覚的に目立たせる。)
③:執拗な繰り返し(例:事業者にとって好都合になるよう、設定を変更するよう繰り返し要請する。)
④:妨害(例:サービスのキャンセルを困難にする。)
⑤:こっそり(例:取引の最後の段階において、自由選択式ではない料金を追加する。)
⑥:社会的証明(例:ほかの消費者の購入行為を通知する。)
⑦:緊急性(例:オファーの期限を知らせるカウントダウンタイマー)
【引用】OECD ダーク・コマーシャル・パターンOECD デジタルエコノミー文書 2022 年 10 月 No.336
ここでは、OECDが刊行するレポート「ダーク・コマーシャル・パターン(Dark commercial patterns)」での類型化をもとに説明していきますね。
①:行為の強制(Forced Action)
「強制(Forced Action)」とは、消費者がサービスの特定機能にアクセスするために、本来不要な操作や個人情報の開示を強制される手法です。
たとえば、商品の詳細を閲覧するためだけに会員登録を強制されたり、利用規約に同意した際に自動的にメールマガジンの購読やプロモーションへの同意が含まれるように設計されている場合があります。
このようなユーザーに望まれない合意や行動を強制することは、個人情報の過剰な収集と選択の自由の侵害につながります。
②:インターフェース干渉(Interface Interference)
「インターフェース干渉」とは、ユーザーに特定の選択をさせるために、インターフェース上(表示画面上)で操作を誘導する手法です。
たとえば、ユーザーにとって重要な情報(事業者にとっては不利な情報)を意図的に目立たないデザインにしたり、文字サイズを小さくして不明瞭にしたりして、ユーザーの注意をそらすものがあります。
また、事業者にとって都合の良い選択肢をあらかじめ固定しておくことで、ユーザーにとっては不要な行動あるいは不利益な設定を促します。
このような干渉により、消費者の選択が事業者にとって有利な方向に誘導され、しばしば不利益な行動を取らされることがあるのです。
③:執拗な繰り返し(Nagging)
「執拗な繰り返し(ナギング)」とは、事業者にとって都合の良い設定などをユーザー自らに行わせるために、繰り返し要求する行為です。
たとえば、通知機能や位置情報追跡の有効化をポップアップで促し、設定しないとページの閲覧ができなかったり、「はい」と「あとで回答する」といった選択肢しかなく、実質的にユーザーに拒否権がないものなどがあります。
このような行為を執拗に繰り返していれば、当然ながらユーザーは意欲を失い、不信感を覚えるでしょう。結果的にサービス離れの加速化に繋がる可能性があります。
④:妨害(Obstruction)
「妨害(Obstruction)」とは、サービスの解約やプライバシー設定の変更など、ユーザーが自身の権利を行使しようとする際に障害を設け、そのプロセスを煩雑、困難にして諦めさせる行為を指します。
たとえば、サブスクリプションの解約手続きの表示画面でメニューを意図的に隠したり、長いアンケートに答えさせたりすることで、意図的に解約プロセスを複雑にする設計がそうです。
また、サービスの登録はオンラインで簡単にできるのに対し、解約手続きではサポートセンターへの電話やメール、書類郵送のみに対応するなど、利便性を意図的に下げる設計も妨害の一種と考えられます。しかもこの手の手口は、なぜかオペレーターに電話が繋がりにくいことが多いんですよね。
このような行為によって、解約や変更手続きを妨害されると、徐々に面倒になり、そのまま同じ商品・サービスを使い続けるといった状況に誘導されてしまうのです。
⑤:こっそり(Sneaking)
「こっそり(Sneaking)」とは、消費者に気づかれように取引条件を変更したり、重要な情報を隠したりする行為で、特にオンライン取引で顕著です。
たとえば、購入の最終段階表示で追加手数料がこっそりと加算されていたり、無料トライアル期間中、終了前の事前通知を送ることなく、ユーザーの明確な同意も取ることなく、自動的に有料の定期契約に切り替わるといったものがあります。
「こっそり(Sneaking)」は、明らかな詐欺的行為とまでは言えないのではと思うかもしれませんが、消費者の意識的な選択の機会を奪い、余計な費用を支払わせたり、意図しない契約に縛られたりするリスクをはらむ手口であることから、やはり悪質と言えるでしょう。
⑥:社会的証明(Social Proof)
「社会的証明(Social Proof)」は、他人の行動や推薦を示すことによって、消費者の購入意思に影響を与える手法です。
たとえば、宿泊予約サイトなどでよく見る、「今、12人がこのページを見ています」とか「本日35人が予約しました」といった表示がそうです。
要は、自分と同じ目的を持った人や行動パターンの似ている人が、行っているとされるアクションやポジティブなレビューを示すことにより、その商品・サービスへの信頼感を高め、購入をあおるのが狙いです。
もちろん、これらの表示が虚偽や誇張で、消費者の誤解を誘引するものになっている場合、違法(景表法違反)になる可能性が高いでしょう。
広告には、消費者の自立した選択を助けるための正確な情報提供が求められます。ゆえに消費者の決定を歪めるために社会的証明を悪用する表示(デザイン)は、消費者との信頼関係を破壊する潜在的行為なのです。
⑦:緊急性(Urgency)
「緊急性(Urgency)」は、消費者に迅速な購入決定を促すために、実際または虚偽の時間的・量的制限を提示する手法を指します。
わかりやすい例として、オンラインショッピングのプラットフォームなどで見かけるカウントダウンタイマーがあります。「期間限定セール終了まで、残り14時間32分」といった表示ですね。
また、「在庫わずか。次回入荷予定は未定です」などの文言で商品の希少性を強調し、「今買っておかないと損するかもしれない」というユーザーの焦燥感を誘引し、衝動的な購入へ駆り立てるのが狙いです。
緊急性を強調すること自体が問題になるわけではありませんが、割引価格と変わらない額でいつでも買えたり、在庫が十分にありながら僅少と偽ったりする表示は虚偽であり、不当表示に該当します。
緊急性をアピールする際には、事実に基づく範囲内で行うのはもちろん、ユーザーの誤解に繋がらないよう、見せ方には細心の注意を払うべきです。
ダークパターンが生み出される理由
ダークパターンは人を欺くためのデザインテクニックですが、多くの企業が意図的にダークパターンを作り出そうとしているわけではありません。
通常、企業には「会員登録数を増やす」とか「LTV(顧客生涯価値)を向上させる」といった具体的な目標があり、それを達成するためにデザイン戦略を立てます。
しかしその過程で、思いがけずダークパターンが生み出されてしまうことがあります。
たとえば、より効果的なデザインを求めてA/Bテストを繰り返す中で、偶然にもダークパターンが選ばれてしまったり、クライアントの要求に応じてデザインを深掘りした結果、意図せずダークパターンを生み出し、ウェブサイトやアプリに組み込まれてしまうことも少なくないのです。
ビジネスの最適化を目指した結果、ダークパターンが生み出されるというのは皮肉な話ですが、ダークパターンが発生する根本的な理由は、売り手の利益を優先し、ユーザーの不利益を顧みない組織の倫理観にあると考えることができます。
というのも、ビジネス戦略を練る段階では、目先の利益追求に焦点があたりがちなので、これがしばしば、ユーザーファーストを無視した決定につながることがあります。
ダークパターンを生み出す構造は、デザイナー個人の力量や裁量にとどまるものではないので、現場の一デザイナーから経営陣まで一枚岩となって、組織全体の問題として捉えていく姿勢が求められます。
企業が利益を追求するのは当たり前ですが、「本当にユーザーのためになっているのか?」を問いかけて倫理的な判断を下していくことは、ダークパターンを生み出さないようにするためだけでなく、消費者との信頼関係を構築し、長期的に売上を伸ばしていくためにも必要不可欠です。
そのうえでユーザー満足度を重視したKPIを設定し、サービスの継続率や顧客体験の向上に組織全体で取り組んでいくことが、ダークパターンを未然に防ぐための重要な戦略にもなってくるでしょう。
海外および国内におけるダークパターン規制の進捗
近年、海外諸国では、ダークパターンを規制する動きが活発化しています。
たとえばアメリカ・カリフォルニア州では、2021年3月15日から「カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)」の改正を通じて、解約手続きなどでダークパターンを用いることが禁止されています。
具体的には、商品の購入をキャンセルする過程で、消費者にとって分かりにくい言葉を使ったり、複数のページへ遷移させるなどして、手続きを妨害する行為を禁じるといったものですね。
またヨーロッパ連合(EU)では、オンラインプラットフォーム事業者などに対し、ネット上の違法・有害情報の削除などを義務付ける「デジタルサービス法(DSA)」を通じて、広告のターゲティングや推薦アルゴリズムに関連するダークパターンを含め、広範なデジタルサービスにおける規制強化が進んでいます。
日本では一部の悪質なものを除いて、ダークパターンを包括的に規制する法律はありませんが、ダークパターンに対処できる可能性のある主要な規制として、景品表示法(優良誤認・有利誤認表示の禁止<5条 1号・2号>)や、特定商取引法(通信販売での、誇大広告の禁止<12条>、最終確認画面における誤認表示の禁止<12条の6第2項>、契約の解除を妨害する不実告知の禁止<13条の2>)などがあります。
たとえば2021年6月1日に施行された特定商取引法の改正では、インターネット通販における詐欺的な定期購入商法、いわゆる「隠れ定期購入」の規制が強化されています。
ざっくり言うと、「初回無料」をうたいながら、実際には定期購入が必要であることを隠したり、申込期間や定期購入の解約条件など消費者にとって重要度の高い内容を不明瞭にする行為を禁止するとともに、明確に記載することが義務づけられました。
比較的新しいところでは、2023年10月から施行された景品表示法の改正があります。いわゆる「ステマ規制」のことで、主に優良誤認表示や有利誤認表示といった景品表示法まわりの規制が厳しくなりました。
いずれの規制も、消費者が明確で信頼できる情報に基づいて、意思決定を行えるようにするための措置であり、実質的にダークパターンの規制を強化するものになっています。
日本国内のダークパターン規制は、欧米諸国ほどスピーディーとは言えないものの、消費者の信頼と市場の公正を守る方向性において、着実に進んでいると考えられます。
ダークパターンにだまされないために(消費者視点)
ごく普通のことを言いますが、まずは「ダークパターン」という消費者を欺くために設計された手法が、ごく身近に存在している事実を認識することがスタート地点になります。
そして具体的にどういったものがダークパターンなのか、種類や手口の事例と踏まえて、正しく理解することが大切です。
お伝えしてきたとおり、ダークパターンは行動経済学や認知バイアス、行動バイアス、ヒューリステイックス(経験則等)に基づいて巧妙につくられていることから、本質レベルで理解に努めていかないと見極めるのは困難です。
するといざダークパターンにだまされた際にも、「ちゃんと確認しなかった自分にも落ち度があった」など自己責任の欠如が招いた結果として受け入れやすくなってしまう。これではダークパターンを意図的に作成した側の思う壺です。
ダークパターンにだまされないために意識しておきたいことの一つが、購入ボタンを押す直前の最終確認画面が表示された際、取引内容や送料、解約条件などの項目一つひとつを入念にチェックにするクセをつけることです。
特に初めて利用するECサイトは勝手も違うため、慎重になるべきです。申し込みを決定するタイミングで、「特別手数料400円」といった見知らぬ費用がしれっと上乗せされていたら要注意です。トラブルに備えて、最終確認画面のスクリーンショットを撮っておくのも有効です。
また、何が引っ掛かるのかがその場ではわからなくても、少しでも違和感を覚えるときはいったん保留にし、冷静になる時間を設けてみてください。

いっときの衝動に流されそうになっているとき、魅力的な言葉や条件でテンポよく誘導されているときこそ、「あれ、これってダークパターンかも?」と疑いの目を向けて踏みとどまることができるだけでも、わりと冷静になれて、論理的な判断ができるようになるものです。
ダークパターンを生み出さないために(作り手視点)
明らかな詐欺的行為はともかく、ダークパターンの多くは違法と言い切れないグレーなところをついてくるため、法律だけでカバーし切れるものではありません。
さらにすべてのダークパターンが、意図的に生み出されているわけではないことも、その線引きをより曖昧なものにしています。
故意にせよ過失にせよ、ダークパターンを生み出さないためには、
・事実ではないことを、本当のことのように伝えてないか?
・ユーザーの焦燥感を必要以上に誘い、判断力を鈍らせようとしてないか?
・意図的にUIを煩雑し、ユーザーに過度な時間や労力を使わせようとしてないか?
といった「ユーザーのためになってないこと」を、一つずつ排除していくことが大切です。
また、効果的なデザインを考えるうえで、競合他社のデザインを参考にすることがあると思いますが、そのデザイン自体がダークパターンである可能性もあります。
成果を出しているクリエイティブが清廉潔白とは限りません。仮にそのデザインを流用した場合、また一つダークパターンが世に放たれることになります。
そのため事例を参考にする際は、「真似すべき部分」と「真似してはいけない部分」をしっかりと区別することが大切です。
そのデザインが効果的に作用している点にばかり注目するのではなく、「ユーザーを欺こうとする要素はいないか」「ユーザーにとって心地良いものになっているか」にフォーカスしてみてください。
ダークパターンの知見を広げたい人におすすめの本

ダークパターンそのものにフォーカスした専門書は、そこまで多くはありませんが、UXライターの仲野佑希氏と、ダークパターンの名付け親であるハリー・ブリヌル氏の著書はおすすめです。
ここでは2冊だけ、サクッと紹介させてください。
『ザ・ダークパターン ユーザーの心や行動をあざむくデザイン』は、UXライターで、UXライティング専門メディア「KOTOBA UX」の開設者である仲野佑希氏の著書です。
主に現場のデザイナーやウェブサイト制作者、デジタルマーケター、企業経営者を対象にしており、商用ウェブサイトでの欺瞞的なデザイン、いわゆる「ダークパターン」に焦点を当てた解説書になります。
ダークパターンがいかに消費者の判断を歪め、個人情報や財産を不正に利用するものなのかの解説が非常にわかりやすく、消費者と作り手の双方がダークパターンの罠に落ちないよう、正しい情報と道徳的な指針を提供してくれています。
また、世界各国で進行中のダークパターン規制の実情と共に、その具体的な例や背後にある原因を、デジタルマーケティングの世界で見受けられる15の欺瞞的手法の事例を通じて紹介。これらがどのように消費者を誤解させるのか、どうすれば避けられるのかといった戦略にもくわしく触れています。
本書は実際のデザインプロセスにおいても非常に実用的で、多くの気づき、学びを得られる内容です。ダークパターンの知見を広げるのはもちろん、ユーザーファーストに寄り添ったデザイン、倫理的なビジネス実践へと導く一冊にもなるでしょう。
>> Amazonで『ザ・ダークパターン ユーザーの心や行動をあざむくデザイン』をチェックしてみる
もう一冊は、ハリー・ブリヌル氏の著書『ダークパターン 人を欺くデザインの手口と対策』です。
こちらは2024年5月28日発売なので、内容はまだ確認できていないのですが、ダークパターンの提唱者であるブリヌル氏の新著というだけで読む価値アリです。
ちなみに書籍の紹介文は、以下のとおり。
「いつまで経っても終わらない退会⼿続き」「すでにチェックされているチェックボックス」……誰しもが経験したことがある苛⽴ちは、わざとデザインされていた。
「ダークパターン(ディセプティブパターン)」の名付け親であるハリー・ブリヌルが、欧米のさまざまな事例を紐解きながらその全貌と、国を挙げての規制強化、今後の展望を解説していきます。
デジタル時代のクリーンなユーザー体験への手引きとなる一冊です。
【引用】Amazon:ダークパターン 人を欺くデザインの手口と対策 単行本 – 2024/5/28
>> Amazonで『ダークパターン 人を欺くデザインの手口と対策』をチェックしてみる
さいごに
ダークパターンを根本的になくすためには、個人や組織だけでなく、社会全体での取り組みが必要です。
極論ですが、全ての人がダークパターンの存在や手口を認識していれば、自ずとダークパターンを避ける力が養われ、それを用いた企業の商品やサービスを選ぶ人はいなくなります。すると企業は「ユーザーをあざむくデザイン」を使えなくなっていくのです。
ダークパターンの意味まで知っている人は、まだ全体の5.7%に過ぎませんが、ダークパターンへの問題意識が社会全体に広がっていくことで、消費者は自身の利益を守れるようになるだけでなく、デザインを制作する側も、消費者をあざむく以外の方法を模索し、健全な企業努力を進めていけるようになるのです。

本記事が、ダークパターンの理解を深めるきっかけ、参考になれば嬉しいです。
ご精読ありがとうございました!
▼ こちらの記事も何気に読まれています!









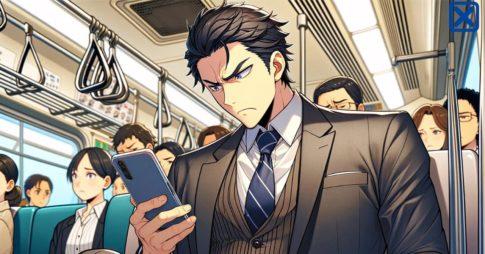




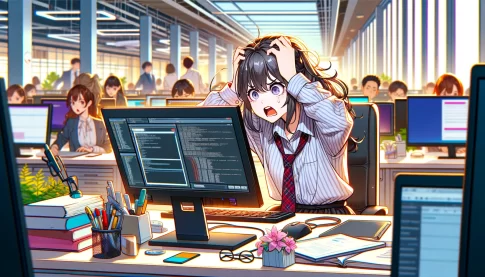





ディセプティブパターン(「ダークパターン」とも呼ばれます)とは、ウェブサイトやアプリ上で、ユーザー(消費者)の意図に反して商品を購入させたり、サインアップさせたりするトリック(欺瞞や策略)です。
たとえば、
・誤解を招く言葉遣いや紛らわしい表現を用いて、ユーザーに望まない購入をさせる。
・購入確定時に登録費用や手数料をこっそり追加し、請求する。
・注文のキャンセル方法を分かりにくくしたり、有料会員(サブスクリプション)の解約案内を意図的に煩雑にし、手続きを妨害する。