ところで、娯楽は2種類に大別されるのをご存知ですか?
「フロー概念」の提唱者と知られる心理学者ミハイ・チクセントミハイ氏いわく、娯楽は“能動的娯楽”と“受動的娯楽”の2つに大別できるというのです。
■ 能動的娯楽

読書やスポーツ、将棋、楽器演奏など、集中力を要し、目標設定とスキルの向上を必要とする遊びのこと。
■ 受動的娯楽

テレビやゲーム、スマホをただ見てるだけなど、集中力やスキルをほとんど必要としない遊びのこと。
能動的娯楽をする時間が長い人はフロー状態(高度な集中状態)に入りやすく、集中力の持続を高める効果が期待できることから、自己成長を促すのに有効なトレーニングになるといわれています。
フロー状態とは、人がその時していることに完全に浸り、精力的に集中・没頭することによって生じる“最適状態の体験”のことです。スポーツでいう「ゾーン」にあたり、『テニスの王子様』でいう「無我の境地」ですね。
このフロー状態とは、一部の人間だけに付与された特別な才能ではありません。たとえば、仕事や遊びに没頭していたら、1日があっという間に過ぎたという感覚・体験も、フロー状態にあったといえます。
一方、受動的娯楽は特別なスキルや集中力を必要としない娯楽であり、自己成長につながりにくいといわれています。
能動的娯楽と受動的娯楽の大きな違いは、自己成長に繋がるか

子どもの頃、親から「ゲームなんて時間のムダ」とよく言われましたよね。
ポテチをつまみながら思考停止でプレイしているだけでは、ゲームの世界における経験値は上げられても、現実の世界での自己成長にはつながりにくいでしょう。
ですがゲームやアマプラ(Amazon Prime Video)、マンガといった受動的娯楽でも、関わり方次第で自己成長をうながせるというのが本記事のポイントです。
たとえばアマプラで映画を観て、「あー、面白かった」だけで終わりなら受動的娯楽でしかありませんが、
✔ その映画を観る理由は何か(目的)
✔ その映画から、どんな発見・学びを得たいのか(知見)
✔ 映画で得た知見を、仕事や勉強、日常生活の場にどう活かすのか(応用)
観る目的を明確にすることで選択的注意が働いて、自分にとって重要な情報を見逃すまいと意識が研ぎ澄まされます。
高い集中力を維持しながら映画に没頭することによりインプットの精度が高まって、脳が受け取る情報量も増えるのです。
アウトプット前提で脳がサボれない状態をつくる

映画を1本観た後で、
・面白かったはずなのに、内容をぼんやりとしか覚えてない
・見どころや概要を、他人にわかりやすく説明できない
という場合、「アウトプットを前提に観ること」が大切です。
たとえば、
・映画の見どころを友達に1分で説明するために観る
・自分のブログでレビュー記事を投稿するために観る
といった感じに映画を観る目的を立てて、それを達成するために「能動的に映画を観なければならない」という状況をつくるのです。
ゲーム同様、ポテチをつまみながら思考放棄で映画をボーッと観ても、ビミョーな感想しか書けず、赤っ恥をかきます。
なので適度にプレッシャーをかけることで、脳がサボれないように追い込み、フロー状態へ入りやすい状態に自分を誘導する。
すると高い集中力、注意力を維持しながら映画に没頭することができるので、内容の理解度が上がり、記憶定着もしやすくなる。
このように受動的に楽しむだけだった映画鑑賞は、アウトプット前提で情報をインプットすることにより初めて能動的娯楽にシフトでき、学びの質を高めます。
映画1本の鑑賞に約2時間をかけているのに記憶にほとんど残らず、これといった学びにもなってないなんてすごくモッタイナイですよね。
ちなみにブログなどで映画のレビューを書いていきたいなら、X(旧Twitter)から始めるのがおすすめ。文字制限があるので要約力を高める良いトレーニングになりますよ。
日常のちょっとしたシーンも能動的にシフトしてみる

大半の娯楽は受動的なので、あなたが娯楽に費やしている時間が圧倒的に受動的寄りであるなら、能動的寄りになるよう工夫してみるといいでしょう。
たとえば私の場合、ゲームは少し前までオフライン専門で、ソロプレイしかしていませんでいた。
もちろんソロでも楽しいのですが、休日を一人、ゲームで終わらせてしまったあとに生じる虚無感が嫌で、もっと達成感のあるものにできないかと思っていました。
そこで職場のライターやデザイナー、エンジニアなどにも声をかけ、ゲーム同好会的なコミュニティを立ち上げました。
すると職場以外でも同僚とのコミュニケーション構築が図れたり、以前仕事をした人とまたコンタクトをとる機会も得られたりして、案件の獲得につながる機会も増えました。
これまで通り目的なくダラダラとゲームを“受動的”に楽しんでいるだけだったら、こういった実利はまず得られなかったでしょう。
また、わたしは電車通勤で毎日45分程度の移動時間が発生するのですが、電車内の中吊り広告やポスターをチェックして、「勝手に添削・提案ゲーム」をやったりして過ごしてます。
たとえば、
「フォントのバランスが悪いので、リュウミンに変えてみたらどうでしょうか」
とか
「見出しの文字が2行にまたがってる必要性があまりないので、1行にスッキリと収めて、一目で情報が飛び込んでくるようにしてみませんか」
とか
「意味が重複している情報を削れば余白ができ、圧迫感を減らせますよ」
といった具合に、消費者とクライアントの視点・利益を考えたうえで、実際に提案するシチュエーションを思い浮かべるといった感じですね。
電車内ってわりと集中しやすいですし、思考停止でスマホをいじって過ごすより、能動的に過ごす時間に変えることでスキルアップも図れるでしょう。
過度の受動的娯楽は“堕落”でしかない

誤解がないように言っておきますが、ストレス解消や疲労軽減などに役立っている実感があるのなら、リラクゼーションの時間として映画鑑賞やゲーム、漫画を楽しむのはもちろん賛成です。
最初に言ったように娯楽は仕事・勉強を頑張るためにも必要なものですし、娯楽があるから頑張れるってもんですよね。
ただし能動的に費やす時間より、受動的に費やしている時間のほうが圧倒的に長い場合は、見直す必要があるでしょう。
というのもゲームやドラマなどの娯楽は「脳が次々に見たくなるような反応」を狙って作られているため、見始めたら止まらなくなる依存性があるからです。
ある調査によると、YouTubeなどの動画を目的なく連続視聴しているときの脳の状態は、ドラッグ中毒者と同じ依存状態にあるそうです。
つまり、過度な娯楽は本来必要ではなく、堕落でしかありません。
また、目的意識が明確だった能動的娯楽であっても、知らず知らずのうちに受動的娯楽へシフトし、惰性化している場合があるので、受動と能動のバランスが偏っていないか、時々見直すことも大事ですよ。
ではさいごに、本記事内容の実践として、アマプラで能動的に映画鑑賞してみましょう。
以下は私がチョイスする、アマプラで無料視聴できる学びの多い映画。どれも普遍の名作ですよ。
①:ショーシャンクの空に(字幕版)(1995年/フランク・ダラボン監督)
②:最強のふたり (吹替版) (2012年/エリック・トレダノ監督)
③:フィールド・オブ・ドリームス (字幕版)(1989年/フィル・アルデン・ロビンソン監督)
④:マイ・インターン(吹替版)(2015年/ナンシー・マイヤーズ監督)
⑤:最高の人生の見つけ方 (字幕版)(2007年/ロブ・ライナー監督)

単なる娯楽でも、明確な目的を持った上で能動的に楽しむ工夫を取り入れることで、新たな発見や学びを得られ、自己成長を促してもいけます。
ゲームやアマプラ、マンガなどの娯楽は、人生をより充実したものにするために必要なものですが、受動と能動のバランスを整えることも大切ですね。
▼ この記事もよく読まれています

















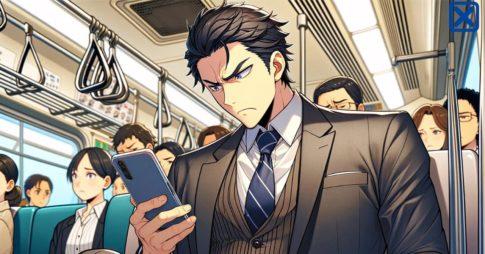



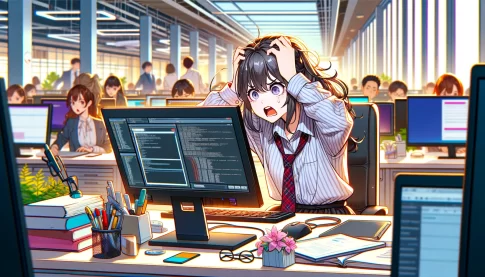
ゲームや映画、マンガが大好きなHiraQです。
娯楽は仕事・勉強を頑張るためにも必要なもの。娯楽があるから頑張れるってもんですよね。