書くための情報を揃え、構成も十分に練った。……なのに筆が進まない。書くことだけに意識を向けて集中できない。
「集中できないのは意志力が弱いから」なんてまとめられがちですが、意志の強さだけで書き続けられるのなら苦労はしません。
人が集中力を持続できる時間の限界は90分と言われていますが、わたしはその半分でもキツイです。なので経験上、自分を集中状態(ゾーン)へと引き上げやすい仕組みを継続するようにしています。
ここでいう仕組みというのは、いわゆる「ルーティーン」です。過去の成功体験があることで一種の自己暗示も働き、常に一定以上の集中力を発揮できるようになりました。
もくじ
①: 場所ニューロンで集中力、記憶力を高める

脳科学では「場所ニューロン」と言って、仕事や勉強をする場所を変えると、集中力や記憶力が高まる効果が、ミシガン大学の研究などでも報告されています。
なぜ場所を変えると集中力や記憶力アップするのか、その理由を簡単に言うと、“覚えた情報” と “記憶した場所” のリンクが考えられます。
脳の仕組みの話として、人は記憶したい内容を単体で覚えるよりも、場所や状況、エピソードなど何かしら関連する内容と紐づけて覚えたほうが記憶に定着しやすいことがわかっています。
記憶する場所が変わるということは、思い出すための手がかりも増えることにもなるので、人の記憶力を司どる器官である「海馬」の活性化につながり、記憶に残りやすくなるのです。
なお集中力は、一度切れると回復に時間がかかるため、完全に途切れてしまう前に場所を変えて仕切り直すのが集中力を高く、長く維持するコツです。
わたしは基本的に在宅ワークですが、家にこもりきりだと集中力がもたないので、毎日カフェに行って2〜3時間ほどノマドワークしています。
カフェでの作業が“日常仕様”になると、「カフェに来たから仕事するか」とマインドが勝手に切り替わ流ので、無理なく自分を動かすことができます。
②:タスク完了後の “ごほうび” を用意する

人は見返りがないとなかなか行動できないもの。そこでわたしは、タスクを完了させた後の “ごほうび” を用意して自分にハッパをかけるようにしています。
ご褒美は「ちょっとアガる程度」でOKです。甘やかすと要求がどんどんエスカレートし、味をしめて効力が薄れてしまうからです。
わたしの場合、このタスクを片したら「セブンイレブンのニューヨークチーズケーキを食べてよし」とか「愛猫との5分間のもふもふタイムを許可する」といったささやかなものです。
要は、「自分的にアガる状況」を意図的につくることでして、この状況のとき、脳には「シータ波」とよばれる脳波が発生します。テキサス大学の研究によると、シータ波が出ているときの学習速度は2〜4倍にもなるとの行動上データもあります。
自分的にアガる状況をつくってシータ波を発生させやすくすることで、前向きな感情で執筆に向かうことができ、集中力の向上が期待できます。
子どもダマシと思うかもですが、大人だろうとご褒美がある場合とない場合とでは、モチベーションに差が出ます。
また、ミッションクリア的なゲーム要素もあって達成感を得られるので、成功体験を積む観点からも効果はてきめんですよ。
③: “33分33秒” のサイクルで無理なく集中力を発揮させる
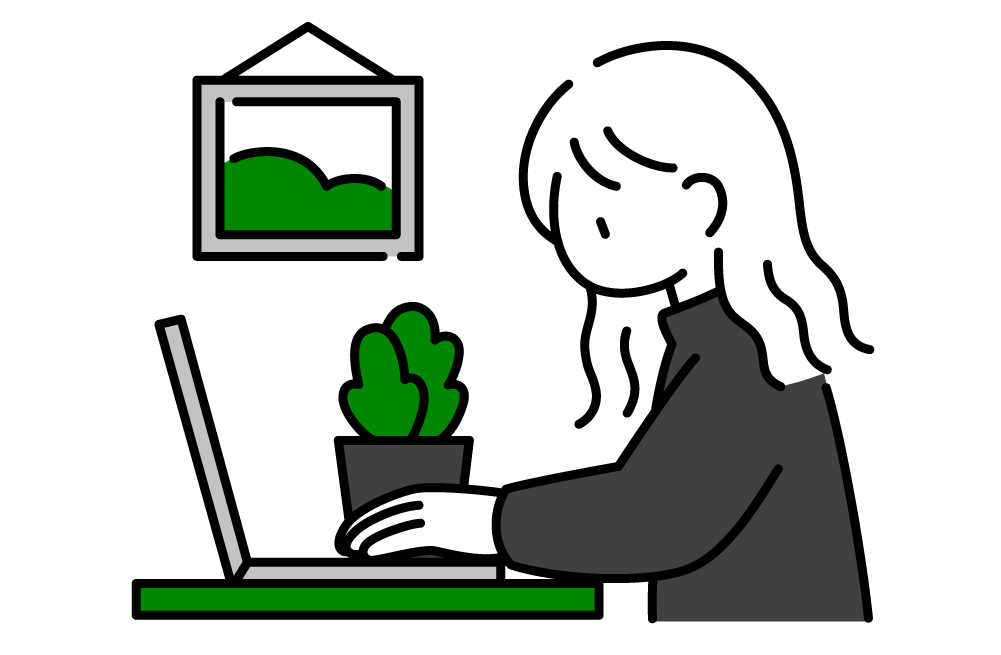
人が集中力を持続できる時間は「90分」が限界といわれていますが、その日の気分や体調、作業環境、タスクの内容等によっては、実際の持続時間はもっと短くなる傾向がみられます。
集中力を持続させるコツは、集中力が尽きる限界まで追い込まずに、「もうちょっとイケる」のところで止めて、常に余力を残すことです。
また、わたしは原稿を執筆する際、タイマーを “33分33秒” にセットし、鳴ったら5分休憩して再開するサイクルを繰り返すようにしてます。
これは「33分33秒の法則」といって、アメリカの伝説的なコピーライターであるユージン・シュワルツが提唱した集中力を長く持続させるのペース配分です。
やり方は以下のとおり。
①:タイマーを「33分33秒」にセットする
②:執筆中は書くこと以外の作業はしないと決める
③:タイマーが鳴ったらキリが悪くても書くのをやめる
④:5分休憩(軽いストレッチや外の景色を眺めるのもおすすめ。5分以上休まないこと)
⑤ :①に戻る
時間管理法は色々とありますが、わたしの場合は「33分33秒」のサイクルが集中力を無理なく維持させるのに適した時間配分でした。
なお「③:タイマーが鳴ったらキリが悪くても書くのをやめる」を補足すると、筆がノッてくるとキリのいいとこまで書き続けたくなる衝動に駆られますが、タイマーが鳴ったら絶対に筆を置いてください。
時間を過ぎても書き続けたらタイマーの意味がなくなるのもありますが、中途半端なところで手を止めることで「ツァイガルニック効果」を発動させるためです。
脳の仕組みの話で、人の記憶は「完了した物事」よりも「未完了のまま残ってる物事」のほうが記憶にとどまりやすいことがわかっています。
そのため作業をキリのいいところまでやってしまうと、脳は「この作業は完了した」のように認識してしまうため、作業を再開する際、もとの集中状態を取り戻すのに時間がかかってしまうのです。
だからタイマーが鳴ったら、中途半端だろうとキッパリやめる。そうすると脳は「まだ作業の途中」と認識しているため、スムーズに作業を再開させることができます。
④:作業前のBGMでスイッチを “ON” へ切り替える

わたしは仕事に取り掛かる前、音楽を2、3曲聴くのをルーティンにしてます。
よく聴くのは、サッカーの「FIFAアンセム」。RIZINテーマ曲の「Theme of RIZIN」。佐藤直紀さんの「DEPARTURE」(TBE系列ドラマ「GOOD LUCK!!」のオープニングテーマ)といったスポーツで使われる入場曲的なものが多いですね。
作業前に気分が高揚する系統の曲を聴くと、スイッチが “ON” に切り替わる感があり、集中状態に入りやすいと感じます。
そもそもBGMは、労働者の生産性を上げるために使われ始めたルーツがあるので、作業前に気分のアガる音楽を聴くことは、「やりたくない作業」へのモチベーションや集中力を高めるうえでも理に適っています。
構成やアイデアを練ったりと、原稿の執筆作業は脳の負荷が大きいタスクです。
なかには「気が進まない」内容だって当然ありますし、手をつけるのが億劫なときもありますよね。
そんなとき、カンタンに脳の状態を「快」へと変化させられる方法が音楽。好きな曲を聴くことでドーパミン(神経伝達物質)が分泌されやすくなり、前向きな気分になれます。
モチベーションが下がると頭が回らず、集中力も上がりません。
わたしは、Spotifyで自分的にアガる選曲リストを大量に作成してストックしてます。
⑤: “デジタルデトックス” を意識した休憩をとる

長時間のデスクワークの場合、こまめに短い休憩時間を設けることで集中力を維持し、疲れを軽減することができます。
わたしの場合、在宅ワークがメインになってからは「デジタルデトックス」を意識して休憩をとるようにしています。
要は、パソコンやスマホなどのデジタルデバイスから定期的に離れる時間を設けることで、集中力の回復、脳疲労の回復効果を高めるのに役立ちます。デジタル中毒に長く陥っている人ほど、デジタルデトックスで得られる実感は大きいと思います。
また、グリーンエクササイズもおすすめ。エクササイズといってもガッツリ運動するわけではなく、公園や湖、河川敷など緑や水の存在を身近に感じられる場所で小休憩するというものです。
近所に川や森、湖がなくても噴水のある公園などのベンチに座って、空や雲、鳥、木などの自然をぼんやりと眺めているだけでも、十分な効果が期待できます。
一日中家のなかで過ごし、パソコンの前からほとんど離れずに受動的に休むのと、緑や水などの自然を感じられる場所に赴いて能動的に休むのとでは、どちらがリフレッシュ効果が高いかは言うに及びません。
⑥: “噛む習慣” で集中力をアップ
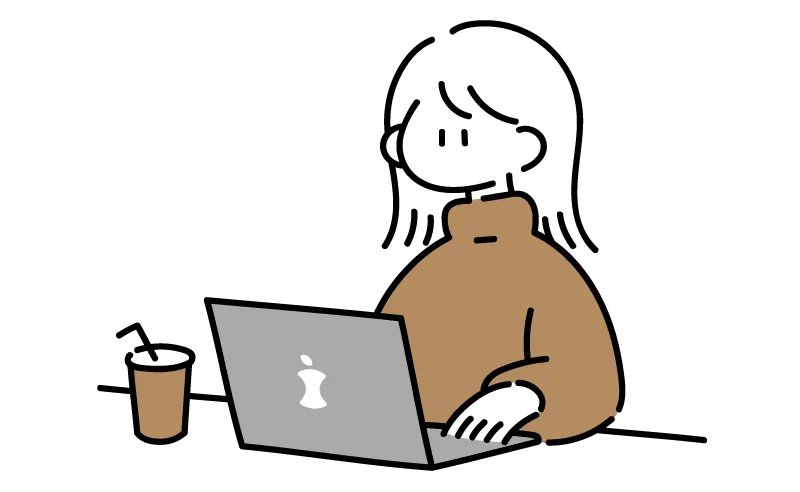
わたしはコロナ禍でテレワークに移行したのを機に、仕事中のガムを習慣づけました。
ガムを噛みながら仕事をすることで、仕事上のストレスや疲労感が薄れ、不注意・仕事の遅れや認知上の問題(勘違い)が減少する(※)ことが、複数の実験や試験結果からも明らかになっています。
【参考】ロッテ噛むこと研究室:「月曜の朝こそ、ガムを噛もう 噛むことと仕事上のストレスの関係」より。
【実験内容】フルタイムで働く大学職員男女126人を対象とした実験で、ガムを噛むグループと噛まないグループの2つに分けて、ガムを噛むグループには一日ガムを噛みながら仕事をしてもらい、ガムを噛むことが仕事の幸福感とパフォーマンスに影響を与えるかを評価したもの。
もともとガムを “噛む習慣” がなかったので恩恵を得やすかったのかもですが、噛んでいなかったときよりも集中が途切れにくく、眠気やイライラを感じにくくなりました。
歯の健康を考えたら、やはりキシリトールがおすすめです。虫歯の原因になる酸を作らず、毎日長時間噛んでいても歯に悪影響を及ぼしません。
同じ味だと飽きるし、噛む効果も薄れてくる感があるので、わたしは複数の味を選べる ロッテ キシリトールガム 7種アソートボトル 143g×6個入 をデスクに常備してます。
⑦: 全てのベースは “睡眠” から

書く作業に限らず、睡眠は全ての活動においてベースとなるものですよね。
質の高い睡眠がとれていれば、気力・体力ともに充実し、高い集中力を発揮しやすくなり、仕事や勉強のパフォーマンスにも好影響を及ぼすと考えられます。
また睡眠の充足度が高いと、「自分をコントロールできている」感覚が得られ、自己肯定感も高まります。
とはいえ質の高い睡眠を毎日とるのって難しいですよね。わたしもたいがい寝不足なので、仕事の合間に「パワーナップ」をとってカバーするようにしています。
パワーナップとは、12時〜15時ぐらいの時間帯に、20分程度の短い仮眠をとること。GoogleやNIKEなどの世界的企業が導入していることでも注目されるようになりました。
ランチをガッツリいった後の午後、眠気がツラいですよね。眠気を気合いでやり過ごすのは非効率なので、仮眠をとった方が効率よく脳の疲れを取ることができます。
仮眠といっても、ベッドに入ってガッツリ寝入る必要はありません。わたしはアイマスクをして軽く目をとじ、イスにもたれかかった状態で20分程度の仮眠をとることが多いです。
机に突っ伏す。イスにもたれかかる。といった体勢のほうが、首にある交感神経節がほどよく刺激されるので効果的です。
注意点は30分以上寝ないこと。完全に横になると寝入ってしまい、ノンレム睡眠のステージ3以降に入りやすくなるので逆効果になってしまいます。タイマーは必ずセットしましょう。
パワーナップで効率的に休むと、午後の作業のはかどり具合が全然違ってきますよ。
⑧: “呼吸が浅い” と集中力が途切れやすい
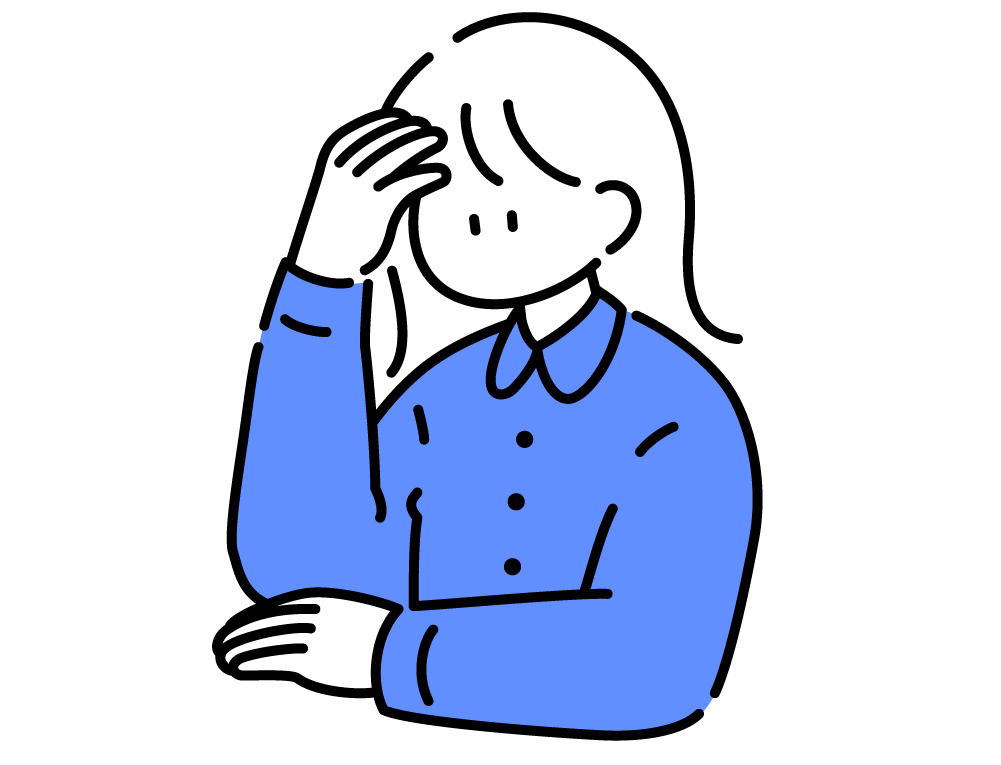
執筆中に集中が切れたとき、「なんか呼吸が浅い。息苦しい……」と感じることないですか?
わたしがまさにそうなんですが、作業中に集中が途切れたとき、両肩が無意識に上がっていて「息苦しさ」を発生していることが多いんですよね。
呼吸が浅くなると脳に十分な酸素が送り込まれず、集中力が途切れがちになります。注意力の欠如や意志力の低下にもつながるため、パフォーマンスが著しく低下します。
普段から呼吸が浅い、深い呼吸がしにくいと感じている人は、両肩が無意識に上がった姿勢を取りがちで、肩や首・胸・背中まわりが常に過緊張でガチガチな人が多いと思います。
首や肩、背中まわりの筋肉が緊張して固まっていると、第一肋骨が上にズレていって両肩が上がります。すると肩甲骨ごと肩が前に出る「巻き肩」の姿勢にもなりやすくなる。
肩が上がりっぱなしの状態が長く続くと、筋肉はその状態を「正常」だと認識するようになり、本来の位置よりも上がった状態がデフォルトになります。結果、呼吸は浅くなります。
対処法は「肩を押し下げる動き」を意識的に行うこと。肩が自然に下がった定位置に戻してあげる必要があります。
わたしは、YouTubeチャンネル「美容整体アピアランスTV」で紹介されている以下のストレッチをほぼ毎日やっているんですが、おすすめです。
動画を見ながら鏡の前でストレッチ前後で比べてみると、肩が明らかに下がっているのわかると思います。
両肩が下がれば呼吸がしやすくなるので、頭がスッキリします。また、首まわりがスッキリすることで細長く見えることから小顔効果もありますよ。
⑨: 締切(デッドライン) を常に設定する

仕事の場合、基本的に締切が設けられているものですが、ブログの原稿などを執筆する際も、締切(デッドライン)を設定すべきです。
締切のない作業は緊張感に欠け、集中力やモチベーションの低下要因になりますし、脳は時間制限があったほうが活発に働きやすくなるという特性があります。
学生の頃、中間テストまで「あと2週間」と「あと3日」とでは、エンジンのかかり具合が全然違ったはずです。
脳に締切を意識させ、危機感をもたせることにより、集中力が発揮されやすくなります。
とはいえ、ギリギリまで追い詰められないと高い集中力が発揮できないようでは、執筆のパフォーマンスは安定しません。
スピード・品質ともに担保するためにも、「ペース上げないとヤバいかも……」くらいのタイトさで、緊張感・拘束感がある強度がいいでしょう。
期限そのものがないタスクもあるでしょうが、ないなら自分で設定するくらいの気概を持つべきです。
時間に余裕がありすぎたり、終わりが見えなかったりすると、怠けや油断といった感情が入り込む余地が生まれてしまいます。
「締切(デッドライン)を常に設定する」。たったそれだけで集中力が高まり、維持する力も授けてくれるのです。
⑩:相手をスケジュールに巻き込んで自分を鼓舞する
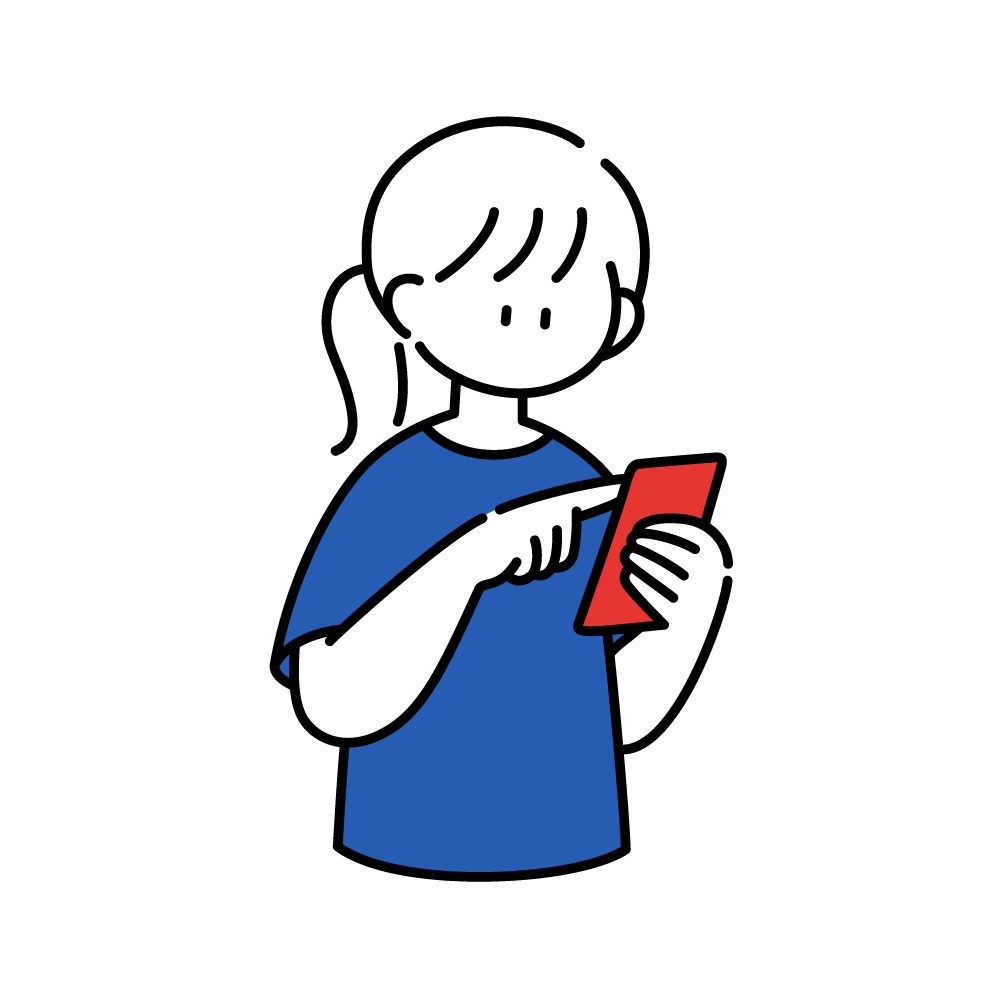
先述の締切効果と付随しますが、わたしは期限が特にないタスクであっても、「8月10日の16時までに提出します」などと宣言するようにしています。
理由は主に2つあって、ひとつは宣言した方が忘れにくくなるから。もうひとつは、相手をスケジュールに巻き込む責任で、自分を鼓舞するためですね。
自分のなかにだけ存在するスケジュールだと、たとえ間に合わなかったとしても、「他にやることがあったから仕方がない」とか「次は気をつけよう」とか「まぁ、誰にも迷惑はかかってないからいっか」みたいに終わるからです。
一方、宣言して相手を巻き込んだ場合、相手はこちらの指定した日時に合わせて、スケジュールを組んだりすることも考えられますよね。
もし遅れようものなら、相手の貴重な時間を奪うだ気でなく、信頼関係にヒビが入る要因にもなりかねません。
相手をスケジュールに巻き込むことで、自分に適度なプレッシャーと拘束力をかけることができます。
脳は時間制限があったほうが活発に働きやすくなる特性があるので、時間への意識も高まり、集中力も発揮されやすくなります。
自分を効率よく動かすための仕組みとして、「周囲を巻き込む」はとても有効だと思いますよ。

おさらいです。気になったところは、読み直してみてくださいね。
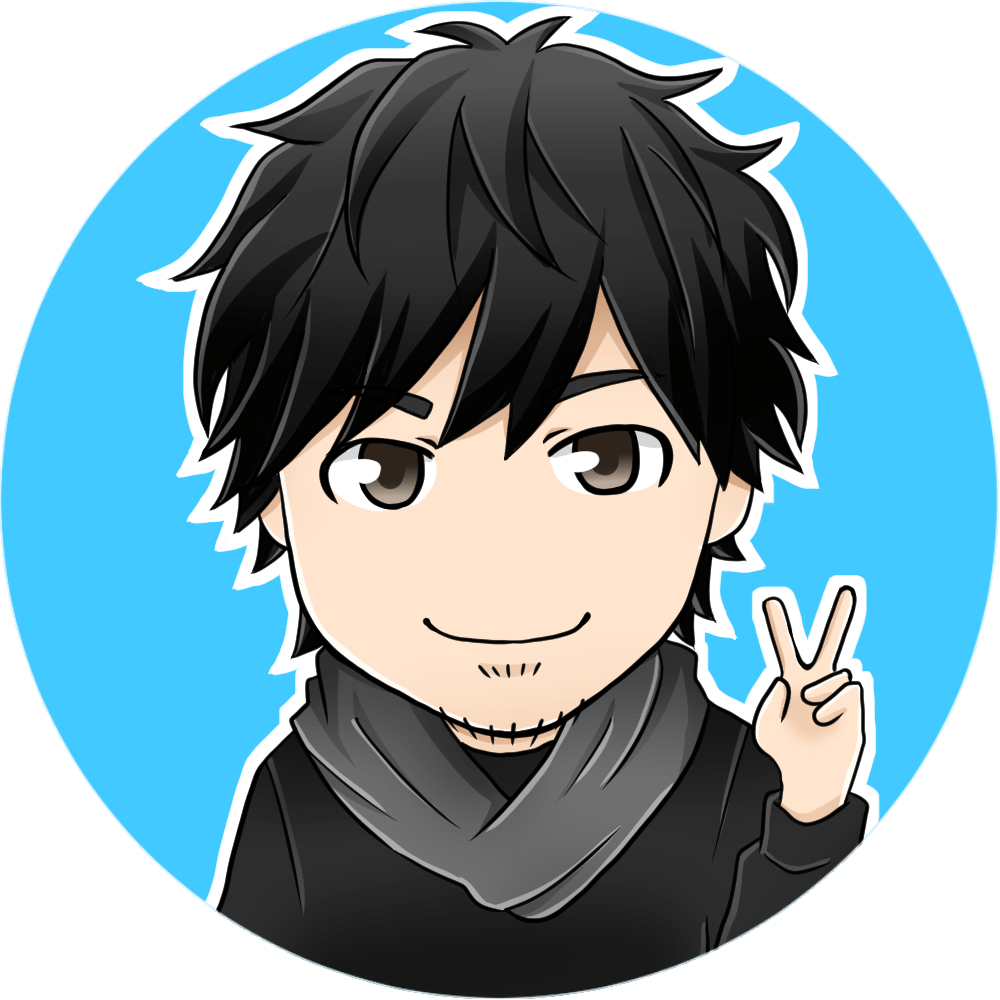
今回は、原稿のライティングに集中できないWebライターのための「10の攻略法」というテーマのもと、特別な準備いらずですぐ始められるものに絞ってみました。
あなたの現在の執筆速度がノコノコだとしたら、モートンくらいにはなれるかもしれませんよ。
本記事が、原稿のライティングに集中できないあなたの一助になれば幸いです。
ご精読ありがとうございました!
▼ こちらの記事も何気に読まれています









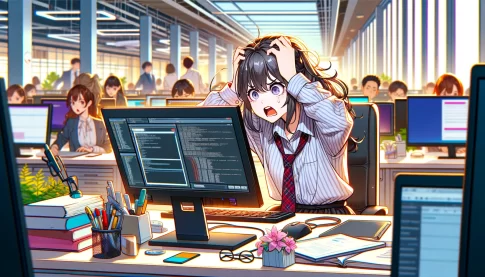










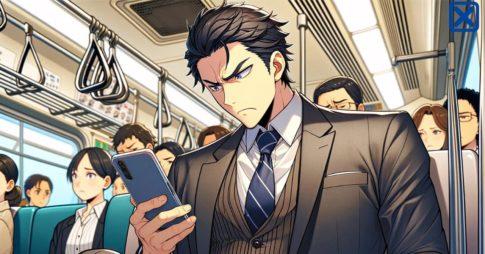

そこで今回は、某広告代理店の編集者兼ライターのわたしが、原稿のライティングに集中するためにやっている「10の攻略法」をお届けします。