私はしょっちゅうです。なかったことにしたいときもあります。
そういう記事の文章って、一言でいえばムダが多い。
カラダでいうと、お腹や足、背中にまんべんなく、ぜい肉が付いてる感じ。
そんなメタボ文章に、だいたい共通してるのが以下の3点です。
✔ 前置きが長い
✔ 余計な内容まで書いている
✔ あってもなくてもいい言葉・表現が多い
人はなぜ、まわりくどい文章を書いてしまうのか
「よし、まわりくどい文章を書くぞ!」と思って書く人はいませんよね。
それなのに冗長な説明をしたり、余計な味付け(アレンジ)を施したりして、物事をかえってややこしく、伝わりにくくしてしまう。
人はなぜまわりくどい文章を書いてしまうのか、私は主に「2つの理由」を考えます。
①:書き手の不安
②:読者ファースト
ひとつ目は、「書き手の不安」です。
人は自分の主張に自信が持てないとき、文章を「盛る」傾向があります。
すると本来、書く必要がないようなことや、むしろ書かないほうがいいことまで付け足して、文章をブクブクと肥やしてしまう。
その結果、文章のキレは悪くなり、情報の濃度も薄まって伝わりにくくなってしまいます。
ふたつ目が、「読者ファースト」です。

これだと言葉足らずで、読者にうまく伝わらないかも……
これだと理由としては弱くて、読者が納得しないかも……
「有益な情報を届けたい」と気概を持って書くことは大切ですが、そこに固執すると文章量がかさみ、黒い文章になっていきます。
黒い文章とは、漢字やひらがな、カタカナの配分比率が偏った文章のこと。文章量が多くなると漢字の比率が高くなり、文章がビジュアル的に黒っぽく見えるようになります。
そうした文章はパッと見、「読みにくい」と感じさせるため、それが「わかりにくい」にもつながっていくのです。

でも情報は多いほうが、読み手だって嬉しいんじゃないの?
情報量が多いのがダメってことではありませんが、原則として、情報量が増えると文章量がかさみ、読了時間も増えます。そのため、読み手の負担は大きくなります。
「情報量が多い」のと「ムダが多い」は全くの別物ですし、「情報量が多いほうが読み手も嬉しい」というのは、書き手の思い込みである可能性が高いです。
こうした事態を防ぐには、
・自分が書きたい情報ではなく、読者が求めている情報を提供できているか?
・読者にとって身近な表現や事例などを用いて、できるだけわかりやすく伝えるための配慮がされているか?
を自問自答問してみるといいでしょう。
書き手目線を外して客観的に読み返してみると、「この部分は要らないな」とか「あってもなくても大差ないな」といったムダに気づきやすくなります。
ブログの文章は小説や評論の世界ではありません。読み手の知りたい情報だけを過不足なく、わかりやすく、簡潔に伝えられるのであれば、それに越したことないのです。

ここからは、某広告代理店の編集者・ライターである私が、実践で得た知見から、「ぜい肉が多いブログ文章を速攻ダイエットさせるリライトのコツ」を解説していきます。
実践しやすく、即効性のある9つに絞ったので、身につくまでの時短にどうぞ。
【即効性あり】ぜい肉が多いブログ文章を速攻ダイエットさせるリライトのコツ9選

① 余計な前置きは削る
世の中には「そんなの言われなくても知ってる。いちいち言わなくていいよ」と読者に感じさせる前置きから始まる文章が沢山ありますが、既知の情報は読む側からすれば退屈です。
なのになぜ余計な前置きを挟むのかですが、理由の多くは「書き手の都合」です。前置きがあったほうが書き始めやすいからです。

でも前置きがないと、唐突な印象になっちゃわない?
たしかに脈略がなさ過ぎるのは問題ですが、その前置きが誰のためにあるのか、記事の冒頭でどうしても伝えないといけないのかは自問する必要があるでしょう。
冷静に読み返してみると、案外なくてもいいと感じることが多いものです。
Webの文章でも書籍の文章でも、読み手の関心を惹きつけられるかは導入部にかかっています。カナダのカールトン大学の研究によれば、ユーザーが訪問したWebサイトの第一印象を決めるのにかかる時間は「0,05秒」だそうです。
そう考えると、優先度が高いわけでもない前置きや既知の情報から始まるというのは、相当リスキーな出だしだとは思いませんか。
よってその前置きがそこまで重要な意味をなさないのであれば削り、さっさと結論なり本題に入ったほうがいい。読者は忙しいので、話が早いほうが助かるのです。
退屈な前置きや既知の情報を「さも重要」とばかりに声高に叫び、読者の貴重な時間を奪ってはいけません。
② なくてもいい接続詞は削る
接続詞は、前後の文をつなぐ導線の役割を果たします。
また しかし けれども よって また そして なぜなら だから すると なので
このあたりはよく使われますが、なんとなくで「また、」「しかし、」「なので、」を使いがちな人は、文章の流れの悪さを強引につなげようと接続詞に頼っていることが多い。
接続詞は前後の文章がスムーズに収まっていれば、なくてもいいケースがほとんど。その接続詞が本当に必要なのか、疑うクセをつけてみるといいですよ。
接続詞を残すかの判断に迷ったら、いったん削り、前後のつながりが悪くなったり意味合いがおかしくなったりするようなら残すといいでしょう。
③「という」は削る
「という」は削っても問題がない場合が多いです。
たとえば、以下のような感じ。
浅草橋に新規オープンしたというカフェ「ルカブルー」のキリマンジャロが絶品ということらしいなので、さっそく足を運んでみた。
▼
浅草橋に新規オープンしたカフェ「ルカブルー」のキリマンジャロが絶品らしいので、さっそく足を運んでみた。
同期の山本くんが支店長に昇格するという話をきいた。そこでサプライズも兼ねて、同期会をやるということになった。
▼
同期の山本くんが支店長に昇格するらしい。そこでサプライズも兼ねて、同期会をやることになった。
上記の「という」には意味がないので、上記のようにするとスッキリ。
もちろん文脈によっては「という」がしっくりくる場合もあるので、「という」を見つけたらいったん削り、不自然になるようなら残すといいでしょう。
④ 修飾語(強調系)はなくてもだいたい通じる
強調系の修飾語は、なくても問題ない場合が多い。削れそうなら積極的に削りましょう。
個人的に「そんなに意味がない」と思う修飾語の2トップが「本当に」と「すごく」です。
たとえば以下のような感じ。
A:新機種が思っていた以上に使いやすくて本当に感動しました。
B:このツールを導入したことで、人件費をすごく削減できました。
どちらも強調の度合いをより強くしたい意図なのだとは思いますが、若干印象がくどく、書き手の「盛り」を感じられます。
また、ビジネスシーンでの「本当に」「すごく」は幼稚な印象を与えかねないため、使い所に注意が必要です。
上記Bでいえば、たとえば「前年と比べて10%削減」といった具合に比較対象を入れたほうが読者の興味を促せるでしょう。
強調系の修飾語はくどさや盛りのニュアンスを含みがちなので、意味合いが変わらないのであれば削ってしまったほうが、読み手に与える印象もよくなりますよ。
⑤「思う」「思います」は削る
そもそも「思っている」から書いているので、「思う」とか「思います」はわざわざ書かなくてもいい場合が多いです。
「思う」の使い方について、言語学者の黒田龍之助さんが、自著『大学生からの文章表現 無難で退屈な日本語から卒業する (ちくま新書)』でにて “抵抗の砦” と解説されています。
「思う」はとても便利である。深く考えずに書き始めた文章が、とりあえず無難に終わる。なんとなくカッコがつくような気がする。さらに「思う」は相手の批判をかわす。どんな主張であろうとも、「これは私が『思って』いることなんだから、他人にとやかくいわれる筋合いはない」と開き直れる。何を「思おう」が個人の勝手なのだ。ということで、「思う」は大人気である。ひょっとしたら「思う」はか弱き者たちの「抵抗の砦」なのかもしれない。
出典:黒田龍之助『大学生からの文章表現 無難で退屈な日本語から卒業する (ちくま新書) 』
このように「思う」は断定を避け、謙虚に伝えたいときなどに便利ですが、多用すると書き手の自信のなさ、責任逃れといったネガティブな印象を与えてしまいかねません。
意識してないけど「思う」「思います」で文を結びがちな人は、使う頻度を減らしてみるといいですよ。
「思う」「思います」に頼らない文章からは、書き手の覚悟のようなものも伝わるので、文章に勢いが出ますよ。
⑥ 「〜することができる」は短縮する
「〜することができる」は、だいたい短縮できます。
私の長所は、最後まであきらめずに努力することができることです。
▼
私の長所は、最後まであきらめずに努力できることです。
これを使えば、あなたも一週間で稼ぐことができます。
▼
これを使えば、あなたも一週間で稼げます。
意味合いは変わらず、見た目はスッキリ。
もちろん「〜することができる」は文法的に間違った表現ではなく「〜することができる」のほうがしっくり来る場面もあるので、文脈によって使い分ければいい。
なお個人的に「〜することができる」は翻訳文みたいなニュアンスを感じられ、若干まわりくどく感じるのであまり使わないですね。
口に出してみて違和感があったら、「〜できる」で短縮するといいですよ。
⑦ 断定を避けてばかりいると、文章にぜい肉が付く
「〜らしい」「〜だと言われています」「〜が一般的です」「〜なんだとか」
上記のような推量・伝聞の言葉・表現は、Webの文章に限らず日常会話でも頻繁に使いますが、、使用頻度には注意が必要ですね。
実際、「〜らしい」とか「〜と言われています」といった言い回しを連発されると、うさん臭く感じますし、「他人の受け入り」といった印象を読み手に与えることから、説得力も弱まりがちです。
自分が読者なら、「〜なのです」とか「研究でも明らかになった事実です」といった具合に自信満々に言い切ってくれたほうが響きますよね。
もちろん断定できない内容もあるでしょうが、曖昧にぼかそうとすると、不自然で歯切れの悪い文章になりがちです。
そもそも他人の記事やテレビの情報をママ流用しているような人は、リサーチの量が絶対的に足りていません。
推量・伝聞に頼った書き方に容易に流されると、言い切る「覚悟」が生まれません。だからぜい肉の多い文章になってしまうのです。
⑧ 本題から脱線した内容は「なくてもいい情報」である場合が多い
・参考までにお伝えしておきたいことがあるのですが、
・こちらは余談で、本件とは離れてしまうのですが、
上記のようなフックを挟んでから、別の話題につなげていく展開ってありますよね。
これは本題と補足したい内容に関連していて、読み手が求めている情報として有益と考えるのであれば、全く問題ありません。
しかし、こういったフックを挟んでから切り出す情報の多くは「書き手が書きたい情報」になっている場合が多く、読み手からすれば「なくてもいい情報」だったりします。
本記事の冒頭では「メタボな文章」の共通項として、以下3つを挙げました。
✔ 前置きが長い
✔ 余計な内容まで伝えすぎ
✔ なくてもいい言葉・表現を使っている
本筋からズレた内容は「余計な内容まで伝えすぎ」に該当します。ゆえに本題から脱線してまで伝えるべき情報かを見極める必要があるでしょう。
ちなみに簡単な見極め方は、文章をひと晩寝かせること。翌日の冷えた頭で読み返してみて「なくてもいい情報」と思えたら削っていい。
本題から脱線した内容は文章を肥やす要因になるだけでなく、読み手を誤解させ、書き手に不信感を与える場合もあります。読み手にとってなくてもいい情報なら、思い切って削りましょう。
⑨ 言い訳言葉は「書き手の保身」に映る
「言い訳言葉」とは、以下のようなものです。
・あくまで「一個人の意見」としてお話しさせていただきますが、
・私の主観であり、異なる意見をお持ちの方もいらっしゃることを前提としてお話しますが、
丁寧で謙虚な切り出し方ですが、若干イラッとしませんか?
不特定多数に向けて何かを主張するのは、勇気と覚悟が要ります。クッションを置きたいのはわかりますが、上記のように「言い訳言葉」が悪目立ちすると、主張に「逃げ道」を用意しているような保身の印象に映る場合があります。

え〜、 そんなつもりで入れてるつもりはないのに……
でも読み手には「それっぽく見える」ものです。正論だからとか内容的に間違ってないからとかは関係なく。
要は「保険をかけるような言い回し」を連発すると、読み手をイラつかせ、逆効果になりかねないということです。
ワンクッション入れて切り出すのは有効な伝え方ではあるものの、そもそも「言い訳から入らないと書けない」のものであれば問題があります。その場合、書き手の主張自体に無理があるか、リサーチ不足が考えられます。
無意識に言い訳言葉から書き始めるクセがついている場合、自信を持って言い切れるだけの情報集めが足りていないのもしれませんよ。
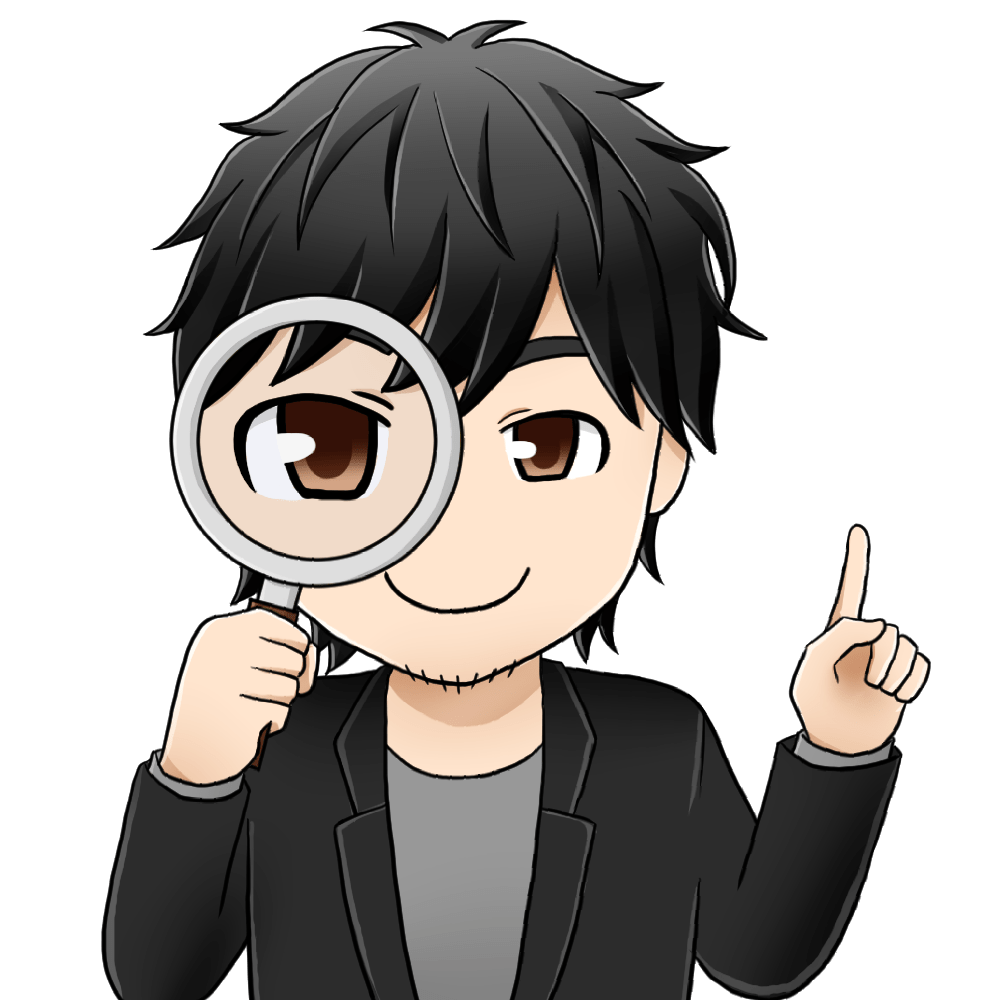
本記事では、ぜい肉が多いブログ文章を速攻ダイエットさせるリライトのコツとして9つのやり方をピックアップしました。
即実践し、ぜい肉を削ぎ落としたスリムな文章を実感してみてください。
ご精読ありがとうございました!
▼ こちらの記事も何気に読まれています!
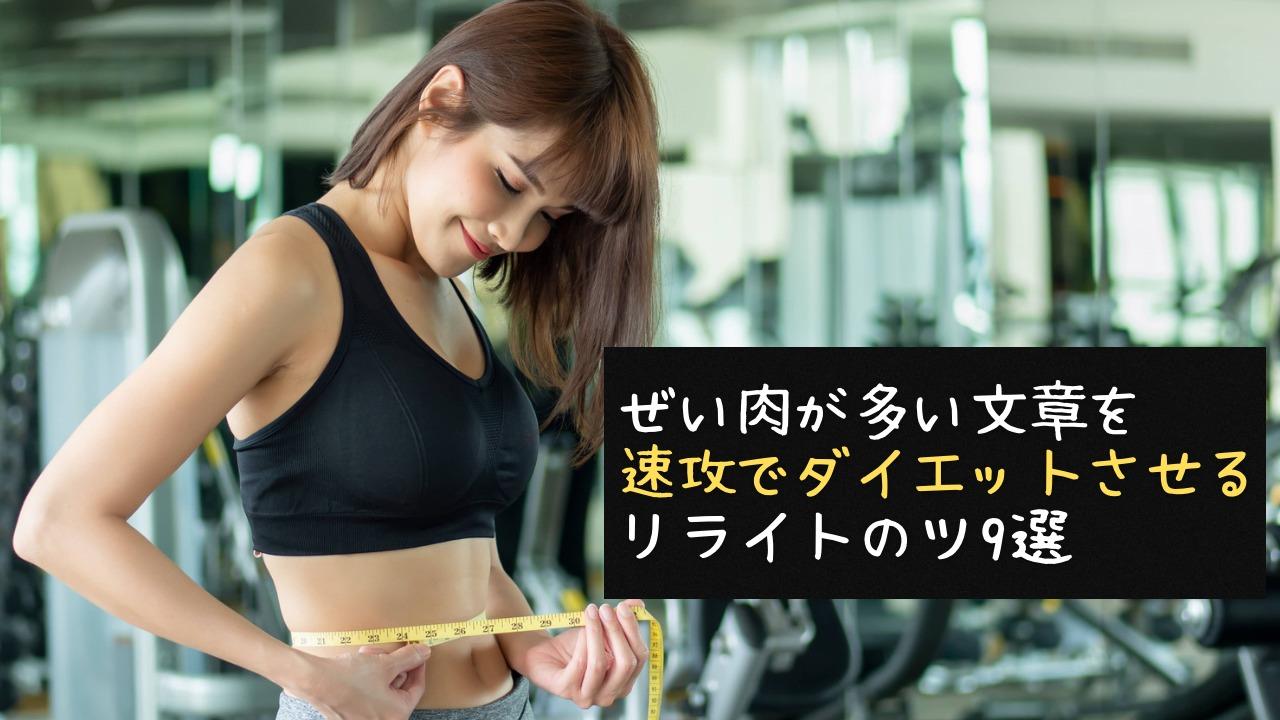



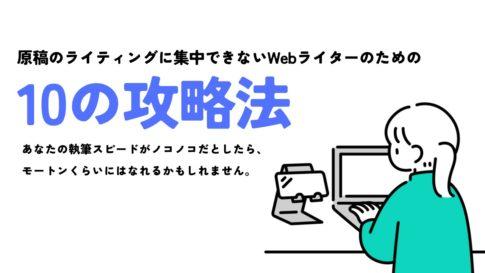





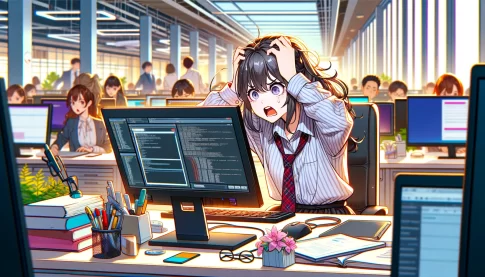








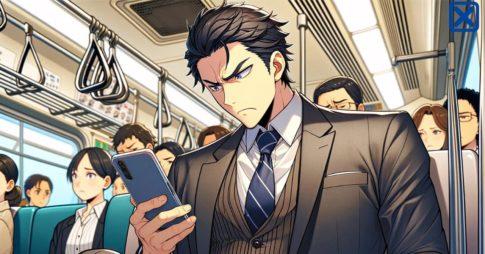


過去に投稿した記事やブログを久しぶりに見返したときに、
「長っ!」
「まわりくどいっ!!」
「わかりにくいっ!!!」
とショックを受けたことありませんか?