実際、過去に書いたブログや企業案件の広告記事を読み返してみると、
・上から目線でエラそう
・なんか説教くさい
・なんとなくイヤな感じ
と感じる箇所がちょいちょいあって、凹んだりします。
戦略上、あえて語り口をキツくしてるとか、要望があってそうしているとかならべつに問題ないのですが、わたしを含め多くの人は、「上から目線で書いているつもりはない」だと思います。
それなのに、「コイツの書く記事は上から目線でエラそう」とか「なんか説教くさい」などと思われてしまうのは心外ですよね。

しかし、何かしら「ムッ」とさせる要素があるから、「なんとなくイヤな感じ」なわけなので、事実として見過ごせませんよね。
ライティングに限らずですが、普段から「上から目線」な物言いになりがちだったり、周囲から高圧的などと指摘されることがあったりするなら、ことさら改善が必要かもしれません。

そこで今回は、無意識に「上から目線」な文章になってしまうのを防ぐための「10のポイント」について解説していきます。
「上から目線」と思われない文章を書くための10のポイント

もくじ
①:教える側のアドバイスは少なからず「上から目線」になる
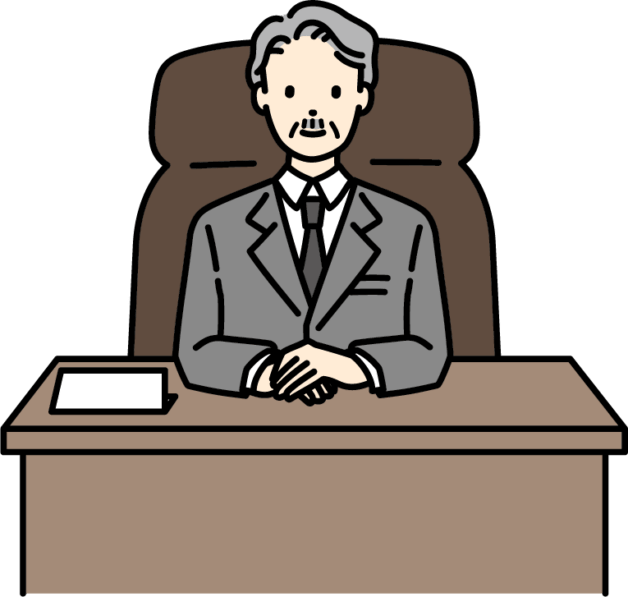
たとえば、ある商品を課題解決型の構成で紹介する記事を書くとしましょう。
その場合、記事の冒頭で読み手の課題を提起し、読み手の抱える悩みや不安に対して共感を示してから、具体的な解決アプローチを提示するといった流れになるのが一般的です。
この展開上、書き手は「教える側」の立場なので、自身の知見や経験則を踏まえてアドバイスするといった流れになることが多いでしょう。
ただし、教える側に立つ時点で少なからず、「上から目線」のニュアンスは出てしまうものです。ゆえに書き手は、その点を十分に自覚して、慎重に言葉や表現を選ぶ必要があります。
多少上からの物言いになっても、読み手に不快感を与えにくくするためには、「権威性をアピールする」ことが効果的です。
たとえば、ブログの場合、著者のプロフィール欄に職業や肩書き、所有資格、実績などを具体的に記載することが有効です。
書き手の立ち位置や、何を根拠にその記事の内容について語ろうとしているのか、記事の冒頭でわかりやすく示すことが重要です。
これは、「先生と生徒」あるいは「師匠と弟子」のような教える側と教えられる側の関係性を明確にするためです。
書き手がその内容について、「語るに足るだけ」の経験や知識を持っていると認識されれば、読み手は聞く耳を持ってくれます。適切にマウントを取ることで、終始、書き手のペースで話を進められるようになるのです。
教える側と教えられる側の立場が明確になることで、多少上から目線の物言いでも反発されにくく、受け入れてもらいやすくなります。
②:否定する前に一度、相手を受け入れる
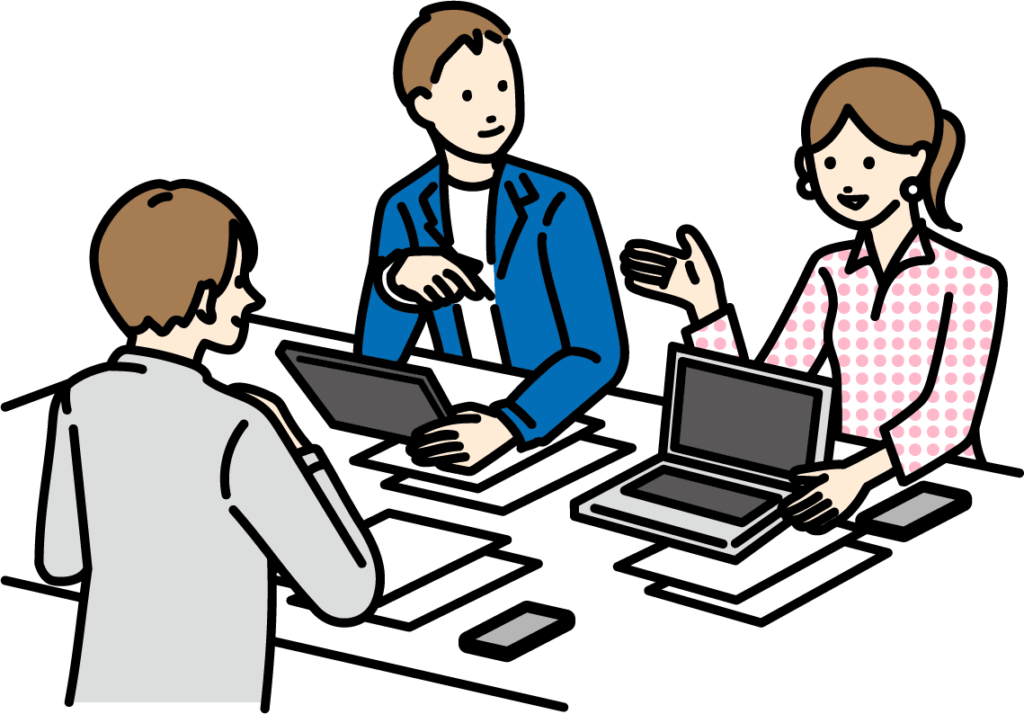
記事の執筆に限らず、何かを否定する意見には上から目線のニュアンスが入りやすいものです。
その意見が正論で的確なものであっても、自分の意見を否定されて気分が良いという人はあまりいないでしょう。
「こいつの言ってることは正しいかもしれないけど、なんかシャクだな」といった具合に、反感を買いやすくなります。
自分の意見を伝えることが、結果的に相手の意見を否定することになる場合、いきなり否定するのではなく、まずは一度受け入れる姿勢を見せることが大切です。自分の主張を述べるのはその後でも遅くはありません。
たとえば以下のようなイメージです。

なるほど! 鈴木さんは△△△というお考えなんですね。よくわかります。とても重要なことですからね。
ただ、わたしは□□□もアリかな〜とは思ってるんです。というのも、鈴木さんにぜひ見てもらいたかった事例がありまして・・・
こんな感じに、自分の意見を伝える(=相手の意見に反対する)際に、相手の意見を一度受け入れてから切り出すことで、相手の承認欲求をある程度は満たすことができます。
「否定する」を「提案する」のニュアンスに近づけることで、否定された側も「上から目線」のニュアンスを感じにくくなります。
こうすることで、「それでですね、実はこういったものがありまして……」といった感じで、意見をスッと差し出しやすくなります。
私見を述べることが、結果的に相手の意見を否定することになるのはよくあることですが、いきなり否定から入るのと、一度受け入れてから否定するのとでは、与える印象が全く違ってくるものです。
③:「あなたのせいではない」と正当化する
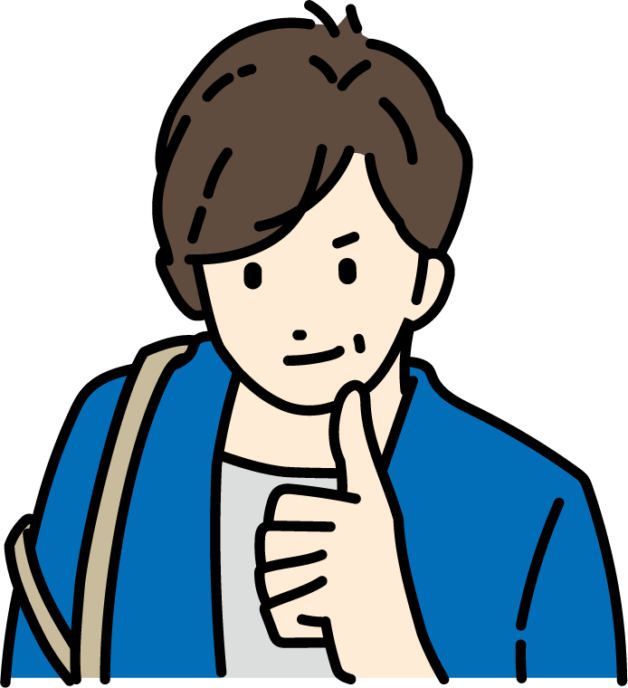
たとえば、TOEICの点数がなかなか上がらない人をターゲットに、画期的な学習方法(商材)を紹介するテイストで記事を書くとしましょう。
このとき、成績が上がらない原因を「あなたの努力不足です」などと定義してしまった場合、身も蓋もありません。「・・・それは否定しないけど」と思うことはあっても、不快感が勝り、離脱する可能性が高いでしょう。
TOEICの点数がなかなか上がらない人というのは、頑張ってないから点数が上がらないのではなく、「頑張ってはいるけど点数が上がらない人」です。
なのでまずは、相手の努力を認め、褒めてあげることから入ったほうがいい。そのうえで、「あなたのせいではない」と正当化するのが効果的です。
相手のこれまでのプロセスと努力に、敬意を払いつつ展開していくことで、読まれやすい流れをつくっていくといいでしょう。
たとえば、以下のような感じです。

「自分の努力が足りないんだ」と自分を責めないでください。
あなたは毎日仕事で忙しい中、時間をやりくりし、勉強時間を確保して頑張っています。そこは褒めてあげてください。誰にでもできることじゃありません。
先に結論から言いますね。頑張っているのに成果がついてこないのは、あなたの頑張りが足りなかったわけじゃないんです。「やり方」が少しよくなかっただけなんです。
でも、あなたが「正しいやり方」を知らないのは無理もないのです。というのは、学校や予備校の先生でも、点数に直結する「正しい学習法」をきちんと教えられる人が圧倒的に少ないからです。
つまり、これまでの努力が報われず、思うような成果を出せてこれなかったのは、あなたの努力不足ではなく、「正しいやり方」をレクチャーしてくれる人がいなかったからなんです。
適切な指導者との出会いに恵まれなかったのは、不運でしたね。でも、もう大丈夫です。あなたは今から、その正しいやり方を学ぶことができるからです。
ただし、最初に言っておきます。このやり方は、誰でも簡単に、即日マスターできる方法ではないということです。
しかし、目標を達成するために努力を続けられるあなたであれば、必ずやり遂げられる方法です。だから自分を信じて、この先に進んでください。
>> 点数に直結するTOEICの「正しい勉強法」とは? (続きを読む)
結果が出なかった直接的な原因を本人の努力不足ではなく、別の原因があったと解釈し、相手を正当化します。
このとき、単なる責任転嫁にならないように注意が必要です。適当な悪者をでっち上げても、読み手を納得させる説得力は生まれません。悪者を設定する場合は、分析と考察に十分な時間をかける必要があります。
最適な原因(=悪者)を設定することで、読み手に「この書き手、なかなかわかってるじゃないか」と思わせ、親近感と信頼感を獲得できます。
「あなたの努力不足が原因ではない」「あなたのせいではない」と正当化した後、「簡単ではないが、努力家のあなたならやり遂げられる」といった形で、相手のこれまでの努力をフックに背中を押してあげましょう。
そうすることで、読み手は前向きになりやすくなり、書き手のアドバイスを受け入れる体勢を整えます。こうして初めて、商品やサービスへのアプローチがしやすくなるのです。
④:書き手の「常識」が、読み手には「非常識」というのはざらにある
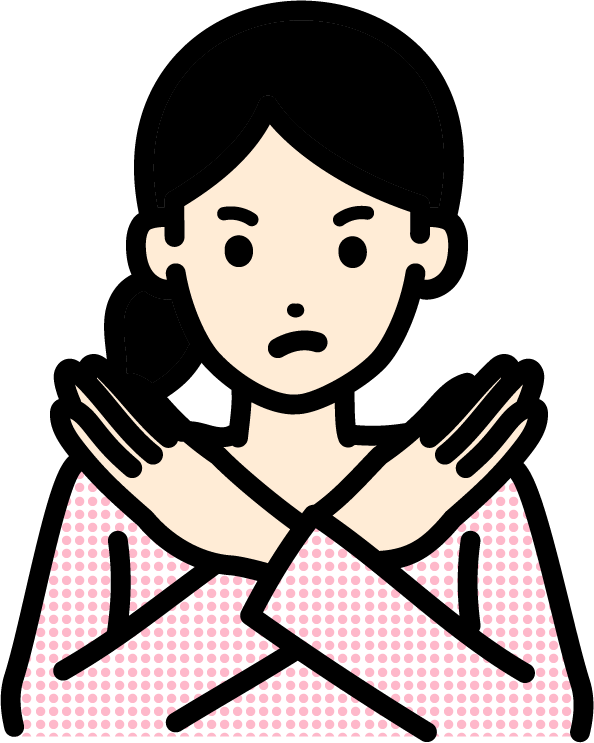
自分の意見を伝える際、「普通は」とか「常識的に」とか「一般的には」といった “前置き” を挟んだりしますよね。
「みんなそう思っている」の大義名分的ニュアンスを醸し出すことができるので使いがちですが、「自分がそうだからみんなもそうに違いない」思考になりやすくなる点に注意しましょう。
よくよく考えてみたら根拠が全くなかったりしますし、知らず知らずのうちに自分基準の「常識」を他人に押しつけてしまっている場合もあり、上から目線のニュアンスが含まれやすくもなります。
ときには自分のなかの常識・ルールを疑ってみることも必要です。かつては世間の常識や「当たり前」であったことでも、時代の流れとともに解釈が変わっていることも往々にしてあるでしょう。
書き手にとっての「常識」が、読み手には「非常識」ということはざらにあります。常日頃から客観的な視点で物ごとを観察するクセをつけて、慎重に言葉・表現を選ぼうとする意識を持ちたいものですね。
⑤:「クッション言葉」で言葉の衝撃をやわらげる

わずかな「イヤな感じ」も積もれば、記事への興味は薄れていきます。
ストレートに伝えると相手に不快と思われかねない場合、「クッション言葉」で衝撃を和らげてから切り出すのも効果的です。
クッション言葉がある場合と、ない場合での違いをみてみましょう。
【なし】ご用意はできかねます。
【あり】たいへん心苦しいのですが、ご用意はできかねます。
【なし】カスタマーセンターまでご一報ください。
【あり】お手を煩わせてしまい申し訳ありませんが、カスタマーセンターまでご一報ください。
【なし】少々お時間をいただけますか?
【あり】差し支えなければ、少々お時間をいただけますか?
【なし】でもそこまで失礼とはならないでしょうが、【あり】のほうが、相手を慮ったニュアンスが感じられるのは明らかですよね。
人は機嫌が良いときほど心を開きやすいものです。クッション言葉を意識するだけで余計な衝撃がやわらぎ、込み入った話も切り出しやすくなります。
クッション言葉はいわば「踏み切り台」のようなもの。話の内容や状況、相手のテンションなどに応じ、ひと手間を添える意識をもってみてみてください。
⑥:自分の黒歴史を打ち明ける
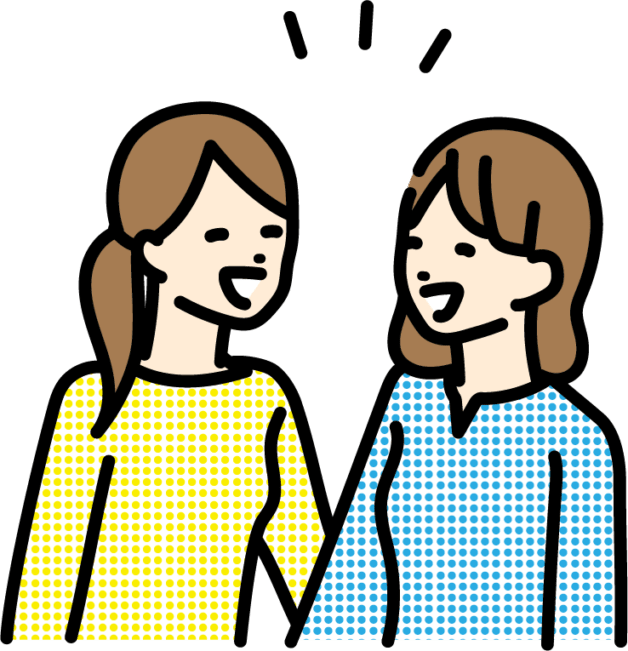
「自分の恥ずかしい過去なんて、格好悪いから話したくない」と思うかもしれませんが、自らが体験した黒歴史を率直に打ち明ける人には、人々が親近感を抱きやすいものです。
これはいわゆる「自己開示」と呼ばれるテクニックで、以下のような感じで使います。
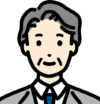
今では副業だけで年収1千万円を超えるまでになりましたが、これまで数えきれないほどの失敗を経験してきました。
お恥ずかしい話ですが、「〇〇(具体的なエピソード)」ということもありました(笑)。
ーーーーーーーーー
※成功するまでの黒歴史を赤裸々に、ときにユーモアを交えたりしながら伝える。
ーーーーーーーーー
しかし、そうした経験があったからこそ、今、あなたがどのような状況にあって、どのような不安や悩みと戦っているのかを痛いほど理解できるのです。
だから今こうして、あなたがすべきこと、してはいけないことを具体的にアドバイスすることができます。
書き手がかつて乗り越えた壁は、今まさに「あなたが乗り越えようとしている壁」と同じです。
つまり「メンター(お手本)」の立場にあるので、書き手は壁を乗り越えるための「攻略法」を知っています。
そんな大先輩が、自分の失敗体験や恥ずかしい過去を正直に打ち明けてくれることは、非常に参考になる話だと思いませんか?
自分とあまりにもかけ離れた人の成功体験は自慢話に聞こえ、あまり参考にならなかったりしますが、「しくじり系」の体験談はいい意味での反面教師。素直な気持ちでメッセージを受け取ってもらいやすくなるのです。
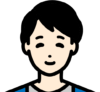
・こんなことまで話してくれるなんて嬉しい!
・こんなすごい人なのに、数年前まではいまの僕と同じことで悩んだり苦しんだりしていたのか!
・失礼だけど、この人でも上手くいったんなら、僕ならもっと早くできるかもしれないぞ!
といった具合に、自信を持つことにもつながるでしょう。
⑦:ポジションが明確なら「上から目線」とは思われにくい
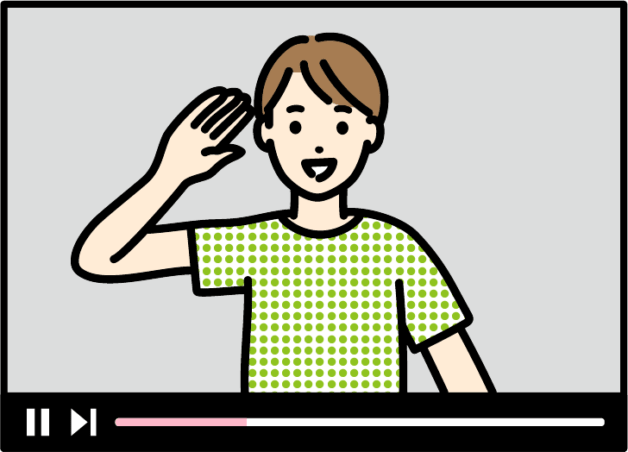
インフルエンサーのブログで、「この人、言い方キツイな」と感じたことがある人を思い浮かべてみてください。たとえば、ホリエモン(堀江貴文)さん、ひろゆき(西村博之)さん、イケダハヤトさん、西野亮廣さんなどを連想される方も多いでしょう。
言い方がキツい人でも、その人のファンとかでなくても、「説得力あるな」とか「それわかる」と納得や共感のできる点があったりするものですが、彼らの発言に重みや説得力を感じられるのは、自分のポジションを明確にしているからです。
文章の世界では「何を書くかよりも、誰が言うかが重要」と言われます。仮に私が堀江さんとまったく同じ内容を発信したところで、大した反響は得られません。それは発信内容が正しいかどうかではなく、権威性がないからです。
発信力のある人は、個々の能力や過去の実績もさることながら、自分のポジションを明確にすることで、自分に優位な間合い(マウントポジション)から主張することができ、権威性をアピールできるのです。
こう言うと、知名度や権威性のない名もなきライターの文章なんて誰も興味ないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
最初にお伝えしたとおり、書き手(あなた)に「その内容を語るに足るだけの専門性がある」と読み手に印象づけられれば、「テーマの語り手」としてのポジションを確立できます。そうなればネームバリューは関係ありません。
権威性がなくても、自分の得意分野、勝てる土俵で勝負すれば、「上から目線」とは思われにくくなるのです。
⑧:人は「自分で決めた」ことなら納得して行動できる
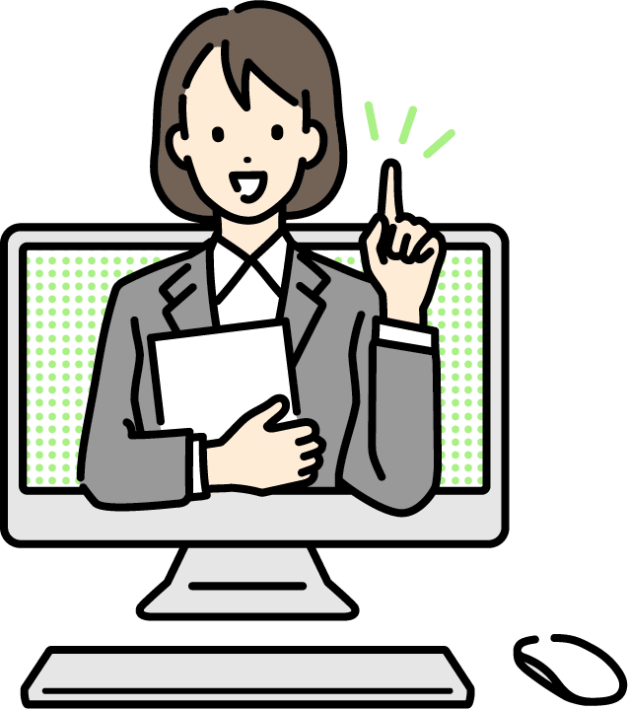
ブログやアフィリエイト系の記事の場合、読者に課題提起を行い、読者が抱える悩みや不安に共感し、「具体的な解決策」を提示する流れが一般的な構成となります。
アフィリエイト記事の場合、読み手に具体的な解決策として紹介するのは、あなたが買ってもらいたい商品・サービスになるでしょう。
他人から勧められたのがきっかけで購入する機会はよくあることですが、人は最終的には「自分の意志で決めた」という納得感が欲しいものです。心理学では「コントロールの錯覚」といって、人は他者が選んだものより、自分の意志で選んだもののほうが価値が高いと感じる傾向があります。
そのため、読み手に商品・サービスを購入してもらうことがあなたの最終目的である場合、読み手に「自分の意識で決めた」と納得感をもたせるような誘導文を考えるということになります。
ちょっとわかりにくかったと思うので、一例を挙げます。
あなたは新しいスーツを買いに、洋服店にやってきました。店内を物色しているうちに良さげなスーツに目が止まり、店員さんがあなたに話しかけてきます。
この時の店員さんの声掛けが、以下のAとBだった場合、あなたはどちらのほうが「試着してみよう」という気持ちになるか考えてみてください。

そちらのスーツ、良い商品ですよ。どうぞ試着してみてください。

そちらのスーツ、良い商品だと思いませんか? よかったら試着してみませんか?
「たいして変わらない」と思ったかもしれませんが、けっこう違います。
Bは「問いかけ」の型になっており、そのスーツが良いものかどうかはあなたが判断することになります。また、試着の決定権があなたに委ねられている点も違います。一方でAは、店員の価値観と願望をあなたに押しつけている型です。
また、人は質問されると「自分がなぜそう答えたのか」の理由を探そうとします。なのでBのように問いかけられると、スーツの風合い・着心地などを確かめたりして、それを「これは良い商品だ」と判断した理由にします。
人は「自分の意思で決めた」という納得感があれば、行動に移しやすくなるものです。一方、他人から行動を促されると、少なからず抵抗感や強制感を感じます。そういった感情が「上から目線」の要因になる場合があるのです。
そのため、「問いかけ」の形式を取り入れることで、意思決定を相手に委ねるようにし、購入や試着といった相手にとらせたいアクションへ導くことが可能になります。
⑨:「です・ます調」の一辺倒になるのもよくない

「です・ます調」は敬体といって、丁寧な意志を表す語を用います。一方、「だ・である調」は常体といって、普通の口語の文体とされます。
簡単に言うと、「です・ます調」は丁寧で柔らかい雰囲気をつくり出すのに使われ、一方の「だ・である調」は断定的で硬い、引き締まった雰囲気をつくり出すのに意識される文体です。
適した文体というのは、記事のターゲット読者層や掲載媒体、伝えたいメッセージ、訴求軸によっても異なります。そのため、読者の興味や関心に合わせて、適切な文体を選択することが重要です。
個人ブログのようなライトな読み物の場合は、「です・ます調」が無難です。読み手にやさしく語りかける雰囲気になり、親しみやすい印象を与えることができます。
ただし、「です・ます調」の一辺倒は避けるべきです。常に丁寧な言葉づかいや表現が続くと、堅苦しい印象からマニュアルのように感じられ、逆に嫌味っぽくなったり、上から目線のニュアンスが出てしまう場合があります。
また、「です・ます調」は語尾が変化しにくく、続けて使用するとリズムが単調になってしまうので、文末で連続して使用しないように体言止めにしたり、「〜ですね」とか「〜しますよ」といった変化をつけることも大切です。
使い所には注意ですが、「!」や「?」といった感嘆符や疑問符、記号、絵文字、顔文字なども取り入れて、文末のバリエーションを増やしておくといいでしょう。
⑩:「読み手の頭の中にない言葉」はなるべく使わない

・日常的に使わない、馴染みのない言葉や表現
・聞いたことがない専門用語や、意味がわかりにくい業界用語
・ 「これ、なんて読むの?」となる難読漢字
上記のような「読み手の頭の中にない言葉」を多用した文章は、読み手に「上から目線」の印象を与え、読む意欲を失わせかねません。
書き手はその分野の知識・経験が豊富なので、専門用語や業界用語を難なく使えますが、大半の読み手はそうではありません。
そのため、配慮なしに「読み手の頭の中にない言葉」を使うと、「これくらいは知ってるよね?」といった書き手の自意識の高さが垣間見え、読み手を「ムッ」とさせる要因になるのです。
誤解しないでほしいのですが、専門・業界用語を使うなって話ではありません。専門・業界用語を使わなさすぎても、かえってわかりにくくなる場合があります。
むしろターゲット(読者層)が絞られていて、読み手に前提知識(専門性)が期待できる場合、積極的に使っていくほうが読み手の理解を助けるでしょう。また、「この書き手は専門性がある」とか「自分と同じ業界の人だ」といった具合に、安心感や親近感を与えることもできるでしょう。
基本的には、誰が読んでも「ちょっと何言っているかわからない」とならない文章を目指すべきであり、そのためにも「読み手の頭の中にない言葉」はなるべく使わないのが前提になります。その上で、読み手のレベルに合わせて調整する柔軟さをもっておきたいものです。
心のどこかで、「教えてやるんだ。ありがたく思え」とか思っていませんか?

そもそも忘れてはならないことがあります。
世の中には数十億ものWebサイトがあり、それ以外にも本や動画、音声など、情報を得る手段は無数にあります。
その中からわざわざ、あなたのサイトに足を運び、貴重な時間を割いてくれたユーザーに対し、上から目線で文章を書くこと自体、失礼すぎるということです。
仮に、あなたが心のどこかで「教えてやるんだ、ありがたく思え」とか思って書いているとしたら、「上から目線」と思われるのも当然でしょう。
私も常に心に留めていることですが、「奉仕の精神を忘るべからず」を意識して書いていきたいものですね。
ご精読ありがとうございました!
▼ こちらの記事も何気に読まれています!
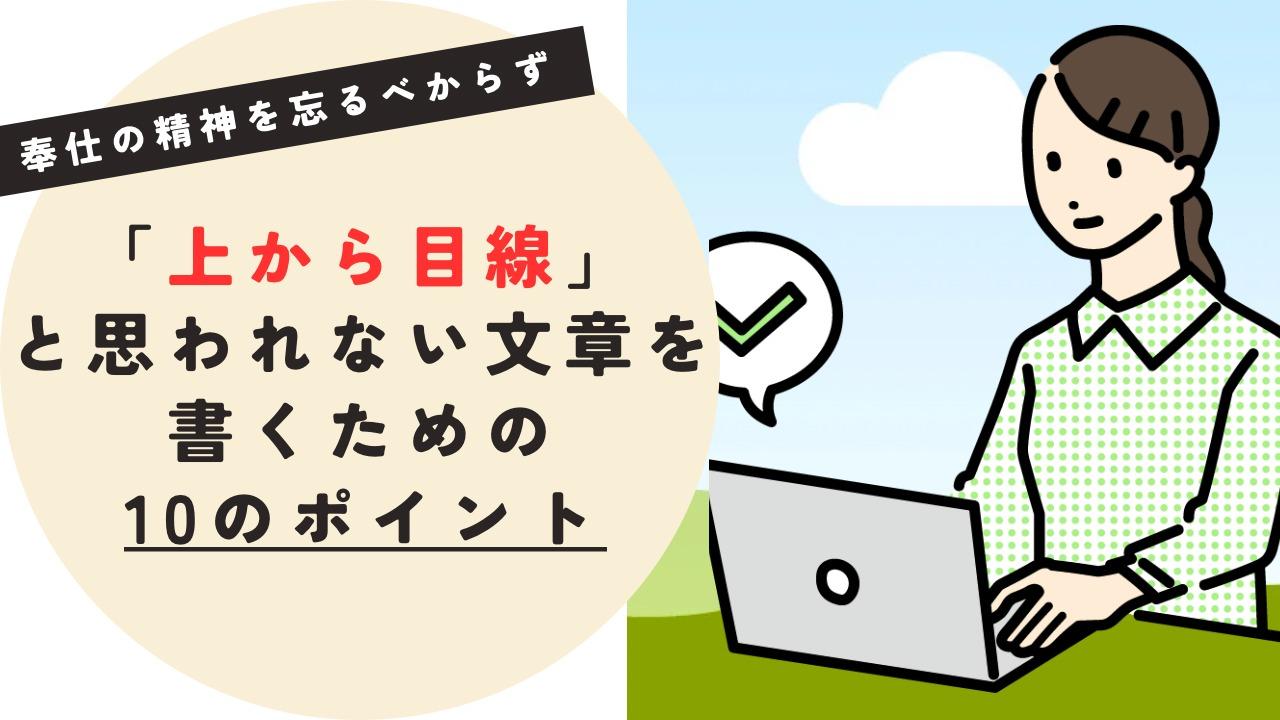


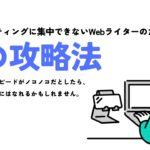



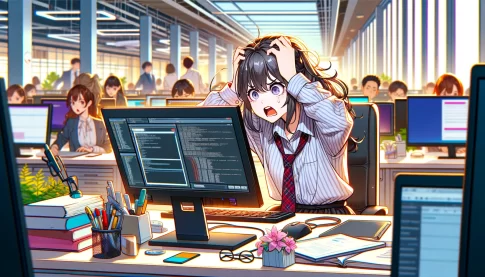













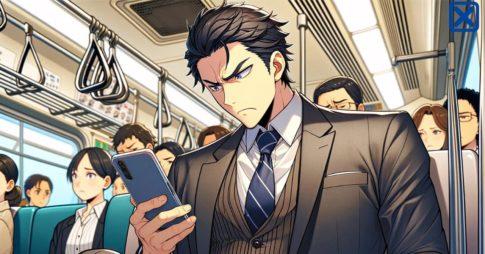

某広告代理店で編集者兼ライターをしているHiraQです。
文章を書くのって難しい……つくづくそう思います。